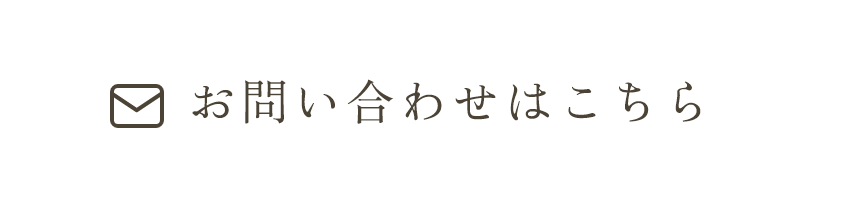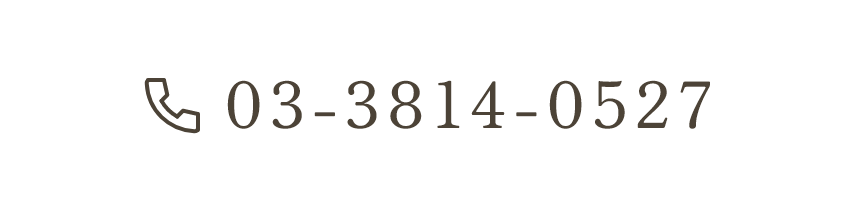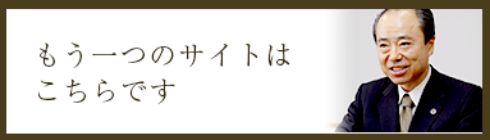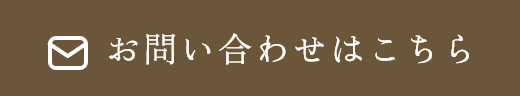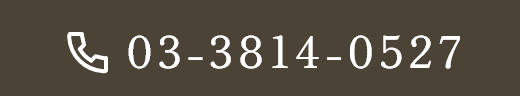FBIの囮捜査への立ち会い

ある日、「上席の役員の1人が、Eメールを脅しの道具にして、ハワイ在住の男に恐喝されているので何とかしてほしい。」という依頼が、顧問先から来ました。脅しのネタは、脅されている本人にとっても会社にとってもかなり深刻なものだったので、放置するという選択肢はありませんでした。脅されている役員と会社は利益相反関係にあるので、役員の代理人に先輩の弁護士をお願いし、私は会社の代理人という布陣を張りました。ここまでは、順調に進んだのですが、次に何をしたら良いのか、相手がハワイにいるだけに皆目見当がつかず、困惑するばかりでした。
何もしないでじっとしているよりは、体を動かした方がマシだろうくらいの考えで、何の見通しもなかったのですが、とにかくハワイに行くことにしました。「脅しのネタを知り得る人物は誰々しかいない。」というロジックから、犯人が誰かの見当はついていたので、現地に着くと、犯人の家を外から見るなど、無意味なことをいくつかしてはみたのですが、もちろん何の役にも立ちませんでした。そこで、日系人の弁護士にチームに加わってもらい、対策について意見交換をし、結局、「ダメもとでも。」というつもりでハワイのFBIを訪問することになりました。
生まれてはじめて、FBIのオフィスに案内されました。「正式に事件を受理しなくても、FBIを名乗って電話をかけることくらいできるが、それで良いか?」「いや、そのような安易なことをお願いしに来たつもりではない。」といった、捜査の要請に対する本気度というか「単に利用しようとしているだけか否か。」を見きわめるためのやりとりがひとしきりありました。こうしたやり取りについては、日本の警察に何かをお願いし、動いていただく時のコツの一つとして心得ており、何度も体験してきたことでしたので、それなりにこなしていったところ、「それでは、事件として捜査しよう。」という、確約をFBIから受けることができました。
それから後は、2~3カ月位だったでしょうか、ひとしきり、犯人とのEメールのやり取りが続き、FBIからは、犯人に宛てて日本から送るEメールの文言についての指示などを受けました。どうやら犯人の要求する金額が当初それほど高くなく、重罪(フェロニー)に届いていなかったので、金額がせり上がっていくようにメールで誘導するのが目的のようでした。そして、要求金額も目論見通り上がった頃、「そろそろハワイに来い。」という指示が伝えられ、空振りになってしまった訪問も1回あったのですが、2回目の訪問で、ついに、現金の受渡しの約束をとりつけることに成功しました。早朝の広い公園の中にいくつも点在するベンチのある小丘の内の一つが、現金の受渡しの場所とされました。現金は、持ち合わせがないというと、FBIが、全部が本物の札束を手提げ袋に入れて用意してくれました。小丘を取り囲むようにして、男女を問わず膚の色も問わず、20人位がまちまちの服装でジョギングしながらまわっていたのですが、彼らは皆FBIのエージェントでした。犯人が登場し、恐喝されている被害者から紙の手提げ袋を受け取った瞬間、ジョギングしていた20人位のFBIのエージェントは、全員小丘に駆け上がり、一瞬「しまった。」という表情になった犯人は逮捕されました。犯人は当然有罪となり、本土の刑務所に収監され、恐喝事件は解決しました。
この事案は、結果的には大成功に終わりましたが、日本人が被害者の犯罪なのに、どうしてFBIが囮捜査までして逮捕してくれたのか、今でもその理由は謎のままです。ことの顛末を知る人の中には、「FBIは、日本のことをアメリカの51番目の州、即ち独立した国家ではないと勘違いしたから、あそこまで捜査をしてくれたんだ。」などという人もいました。それはともかく、この事件は、犯人がハワイ州在住、被害者がハワイ州非在住という州際性があることに加えて、距離の離れた犯人と被害者を結んでいたのが当時一般化し始めていた「Eメール」だったことが、FBIの関心を引いた、ということだったのだと思います。
保険金詐欺に対して弁護士が関与し始めたころ

昭和63年(1988年)10月に火災事故が発生したのですが、この火災事故に対して保険会社は放火の疑いが強いと判断し、保険金の支払を拒絶しました。火災保険の保険金を巡って争いが生じ、当時「社会運動等標榜ゴロ」と呼ばれていた一派が介入してきました。彼らは、保険会社の本社の社内に、映画の撮影カメラのような、今では考えられないくらい大げさなものまで持ち込んで、居座ったりといったこともしてきました。しかし、保険会社は、こうしたことに動じませんでした。私も、早い時期からこの事件に関与し、保険会社の支払拒絶をサポートしていたところ、この事案は、結局、平成2年(1990年)に大阪地裁に提訴されることになりました。
こうした、保険事故のような偶然の事故を装って、故意の事故をでっち上げ、損害保険金を詐取しようとすることを、モラル・リスクといいます。今では、モラル・リスクに対抗する手段として訴訟を選択することは、さして珍しい方法ではなくなりましたが、この大阪地裁の訴訟は、そうしたモラル・リスクに対する訴訟対応のリーディング・ケースの1つでした。幸運だったのは、訴訟の中途で原告(放火をして保険会社から火災保険金の支払いを受けようとした張本人)が全く別の詐欺の刑事事件を起こし、有罪の実刑判決が下されたことです。そのために、原告が収監されている刑務所の所内で、原告本人尋問をするという「めったに出来ない」体験ができたこともありますが、その「別の詐欺事件」の刑事一件記録が入手できたことが、望外の幸運でした。刑事記録のどこが一番重要か、理解できずに、全部を民事の裁判所に出したのですが、裁判官は、ある捜査報告書に添付されていた「原告の時期別負債状況の推移」という書面を、判決書に添付までして重視しました。私は、この様な裁判官の証拠の評価の仕方を目の当たりにして、「借金(もう少し広く言うとすれば、問題を起こした時の、当人の経済状況)を『詐欺の故意』を推認するための間接事実として重視する」という発想を、学ばせてもらいました。
この事件は、「故意の事故招致」までは認定してもらえなかったものの、平成6年10月11日に、「損害の不実申告」で勝訴し、原告との関係では地裁で確定しました(判例時報 平成7年4月1日号、No.158、117ページ以下、判例タイムズ 平成7年2月15日号、No.864、252ページ)。
フィルム・ファイナンスの日本への導入

タックス・ディファーラルという節税手法があります。ある年度に、とても儲かった個人や会社が、何らかの理由で減価償却の期間を特別に早めることが認められている償却資産を購入し、減価償却を行うことでその年度の課税対象所得にかかる税金の支払を圧縮させ、その償却資産の購入に要した資金は、あえて名前を付ければプロフィット・デファーラルとでもいうのでしょうか、翌年以降にその償却資産が稼ぎ出す売り上げによる回収を目指すという節税方法のことを言います。よく使われた償却資産は、映画の著作権やオイルリグと呼ばれる石油掘削(試掘)に使われる機械で、もう少し規模を小さいものにした場合、ヘリコプターなども利用されました。もっとも、日本では、伝統的に「節税」に対するアレルギーが強く、タックス・ディファーラルという節税手法を広めようという日本人は、それまで現れてはきませんでした。
そんな中で、ハリウッドの映画製作の資金提供者として、ニューヨークで活躍していたイギリス人が、日本で、ハリウッドの映画製作に投資するための資金を集めたいと、当時私が勤務弁護士として所属していた法律事務所にクライアントとしてやってきました。このクライアントは、米国をはじめ、いくつかの国で、「フィルム・ファイナンス」という映画の著作権という償却資産に着目したタックス・ディファーラルの手法で、資金集めをしていた人でした。当時は、日本の映画の著作権にも、8か月といった極端に短い「特別償却」の期間が認められていましたので、「フィルム・ファイナンス」は、タックス・ディファーラルの中でも、節税のインパクトが大きいものでした。もっとも、その裏腹のようなことになるのですが、「フィルム・ファイナンス」の場合、翌年以降に生ずる利益、即ち、上映料や放映料あるいは二次的利用の対価などに確実性を見込めないという大きな欠点がありました。そうはいっても、購入する映画に対しては、大ヒットすればいうことはありませんが、ある程度ヒットすることは、投資家から当然期待されます。こうしたニーズに対して、来日してきたクライアントは、一つのディールあたり「3本」の映画の「著作権」の購入をセットにしていました。数学的根拠は分かりませんが、何でも、コストパフォーマンスは、「3本」が最高なのだそうです。1本や2本では、ヒットする確率が低すぎる一方、3本を4本や5本に増やしても、追加される資金の割には、ヒットする確率はあまり大きくならないということでした。もちろん、「フィルム・ファイナンス」の主催者は、投資の対象とする映画の選別の達人(翌年以降に利益が生ずる映画かどうかの目利き)としての評判も得ていなければならず、やってきたクライアントはそういう意味でも優れた実績と見識を有しているとの評価を受けている人だ、ということでした。
この、「フィルム・ファイナンス」というスキームは、日本への初導入だったので、「パス・スルー課税」や「倒産隔壁」などの論点との関わりで、集めた資金をプールする器の法形式について、民法上の組合や匿名組合の性格を多方面から検討し、何とか実務に耐えるパッケージに作りあげました。その1年後くらいだったでしょうか、このパッケージは、ある、アメリカの著名な銀行の日本支店の法務担当者に、そっくりそのまま、デッド・コピーされました。いい気分のものではありませんが、どこにも手が入れられていなかったので、真似をされたスキーム自体の出来は良かったということになるのかもしれません。
しばらくすると、映画の特別償却の制度もなくなってしまい、「フィルム・ファイナンス」は、その存立基盤を失ってしまうのですが、その前に、クライアントは、日本の様々な人や会社にこのスキームの営業をして回ったとのことでした。しかし、この「フィルム・ファイナンス」というタックス・ディファーラルのスキームは、日本社会のエスタブリッシュメント層には見向きもされず、興味を持って集まってきたのは、首をかしげたくなるような人たちばかりだったということでした。多分、デッド・コピーをしたアメリカの著名な銀行の営業成績も似たようなものかそれ以下だったと思います。「フィルム・ファイナンス」は、日本社会には、受け入れられませんでした。
しかし、タックス・ディファーラルというスキームがすべて拒絶されたというわけではなかったようです。日本にも「航空機のリース」というタックス・ディファーラルのスキームは社会に根を下ろし、現在も続いています。「フィルム・ファイナンス」、と比べると、この「航空機のリース」というタックス・ディファーラルは、特定の年の節税のインパクトより、二次的利用の対価に対する確実性の方が大きいという性質を有しています。あるいは、こうした性質が、日本という国に適合的なのかもしれません。
複合一貫輸送の報告書の迷走

1970年(昭和45年)代以降1990年(平成2年)代半ばまでは、日米貿易摩擦の時代でしたので、アメリカは、日本に対して、市場の開放を迫り、日本には貿易不均衡をもたらす構造的な障壁があるので、それを取り除かなければならないと、ことあるごとに、日本に迫ってきていました。当時、そうした構造的障壁の一つとして、複合一貫輸送が取り上げられていました。複合一貫輸送というのは、米国のトラック輸送、船舶の輸送(あるいは飛行機の輸送)、日本のトラック輸送を同一の米国なら米国の輸送業者が一気通貫的に行うという輸送モデルのことで、IMMTO(Inter Model Multiple Transformation Organization)と呼ばれていました。当時、日本では、米国の貨物は、米国の業者が宛先である日本の戸口まで送り届けることが禁じられていたのです。
そうした日米貿易摩擦の解決のために1995年に設立されたのがWTOという仕組みでしたが、WTOができても、日本の複合一貫輸送に対する規制が撤廃されることはありませんでした。
そうした社会情勢を背景として、ある日、当時私が勤務弁護士として所属していた法律事務所に、フライング・タイガー・ライン社というペンタゴン系として知られていた国際航空貨物会社から、仕事の依頼がありました。それは、「日本では、どうして米国の航空貨物会社が複合一貫輸送をしようとしてもできないのか、その理由を調査してほしい。」というものでした。
私が、この件を担当するようにと指示を受けました。私は、何時も行っている案件の一つとしてこの件を受けました。私は、「調査」といっても、ややとりつくしまもなかったので、「何かヒントになることを教えてもらえるかもしれない。」といった軽い気持ちで、通産省を訪問し、若手のキャリア官僚に「そのわけを教えてもらえないか。」と尋ねてみました。するとこの官僚は、「交易の自由化を定めたOECD Codeには、末尾に、列挙された特定の事項については、加盟国が例外を定めても良い、という例外措置許容条項が付されており、列挙された事項の中に、『国防にかかわることは例外としてよい』という条項がある。日本では、『複合一貫輸送』は『国防』にかかわることという位置づけている。だから、自由化の対象から外されているのだ。」と説明してくれました。
私は、この調査結果をまとめた件で共同作業をすることになっていた外国人の若手弁護士に通産省の若手官僚から聞いたことを説明し、彼が「報告書」を作成し、事務所の上司の弁護士が、その「報告書」をフライング・タイガー・ライン社に渡して、この件は、事務所的には区切りがつき、案件としては終了しました。
しかし、アメリカでは、次元の異なる事態が始まることになってしまったようでした。ここからは、聞いた話で、資料などを直に確かめたわけではないのですが、私が所属していた法律事務所からの話によると、渡された「報告書」は、ペンタゴン系の会社であるフライング・タイガー・ライン社の手で、アメリカの高名な大学の高名な教授に渡されたそうです。その高名な大学の高名な教授は、ご自分で調査した結果だといった額縁を添えて、「報告書」の内容を、センセーショナルにアメリカの政治家やアメリカの人々に伝えて回ったということでした。米国の議会でも証言したということでした。ここまでくれば、多分、『複合一貫輸送』をOECD Codeの例外とするスタンスは、維持できなくなったのだろうと思います。
この顛末は、私にしてみれば、良い気分でいられるはずもないものでしたし、私の質問に答えてくれた通産省の若手のキャリア官僚に対しては、倫理的な負い目を感じざるを得ませんでした。
のちに、フライング・タイガー・ライン社という会社は、第二次世界大戦に参戦した「義勇軍」が母体となって設立された航空貨物会社で、朝鮮戦争の時やベトナム戦争の時には、特需で業績が良かったけれど、1970年代の半ばにベトナム戦争が終わると、徐々に勢いを失い、1980年代の終わりの頃には消滅してしまった会社だと知りました。日米貿易摩擦というのは、こんな会社が活躍する場だったのかと、あらためて思い知らされ、複雑な気分が、なお一層強まりました。