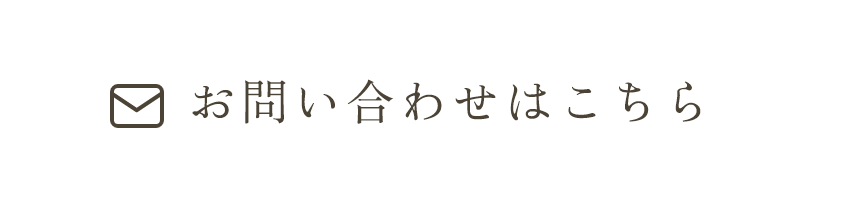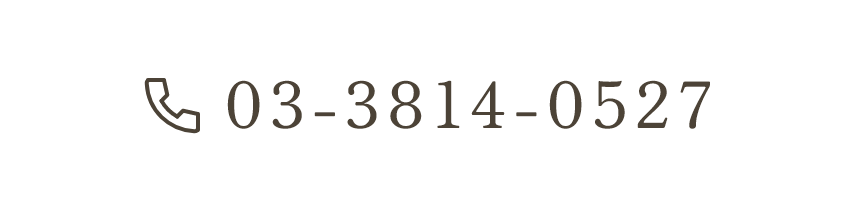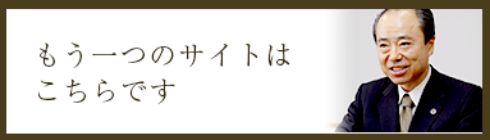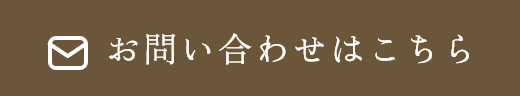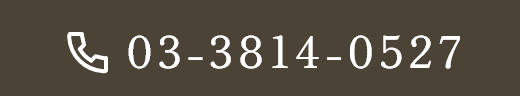「地理的救済」という言葉

私の小学生時代は、多分、体育や美術などをのぞけば、成績は相当に良かったように記憶していますし、いじめられたり引きこもったりということもあるはずもなく、普通に考えれば、何一つ不自由のない幸せな毎日を過ごすことができたはずだったのですが、私にとっては、そうではありませんでした。その本当の理由は、今でも不明です。とは言うものの、私は、自分の気持ちの上では、ものすごく自己評価の低い児童だったということが、大きかったのではないかと思っています。私は、私が自分のことを低く考えるのと同じように、周りのクラスメートからも、なぜか見下されているような感じから抜け出すことができないでいました。
そんな私に、思わざる転機が訪れました。それは、サラリーマンだった父の転勤のため、小学校6年生(1965年)の時に、東京の学校から、愛知県の学校に転校しなければならなくなったという出来事によるものでした。
私が東京にいたとき、私は、まわりにいたクラスメートが、皆、一様に、「私が何とはなしに引け目の根拠だと思い込んでいた小さなエピソードの積み重ねのことを知っている。」と信じて疑いませんでした。しかし、愛知県に転校してしまえば、そこにいるクラスメートの中には、そのようなことを知っている人など一人もいません。私は、「これで、自分は、自分に対してネガティブだった周囲の目から解放されたのだ。」と、一人合点で、確信しました。そして、中途で編入した小学校の6年生の時もさることながら、とりわけ、中学校に入学してからというもの、少し大げさですが。精神の自由を満喫して、学生生活を送れるようになりました。
「自分に訪れたこの強烈な変化は、いったい何なのだろう。」そんな疑問を抱きつつも、それ以上考えを進めることもできないまま、快適な毎日を過ごしていたある日、私は、ふと手にした新聞の文化欄の中の大きめな誌面に、寺山修司が永山則夫のことを論じているコラムが掲載されているのを目にしました。そのコラムの中で、寺山修司が永山則夫の何か所目かで何人目かを殺したという行動にまつわる問題を象徴的に表現するための、「特別あつらえの一対の用語」として使っていたのが、「時間的救済」と対比された「地理的救済」という言葉でした。私は、「時間的救済」のことを「その場にとどまって、地道な努力を重ねていくことによって実現することのできる問題の解決の方策」、「地理的救済」のことを「その場から遠く離れてしまうことで、瞬時に手に入れることのできる問題の回避の方策」と理解しました。こうした理解は、勝手読みにすぎなかったのかもしれませんが、私は、この寺山修司の論稿を見て、「そうか、自分は今、『地理的救済』の恩恵にあずかっているのだ。」と強く感じたのです。「地理的救済」には、単なる逃避の手段という側面もありそうです。そう考えると、あまり褒められたことではないのかもしれません。しかし、当時の私にとっては、そんなことはどうでも良いことでした。当時、私は、「わけはわからないけれど、多分、東京から愛知への移動がきっかけとなって、すっかり居心地に大きな変化が生じた。この今の自分のよって立つ基盤は、いったい何なのだろうか。」という疑問に表現を与えてもらい、客観性を付与してもらったこの「地理的救済」という言葉との出会いに、小躍りしたいほど、うれしくてたまらなかったのです。
今、その新聞は、もちろん手許にはありません。寺山修司が書いたものを、ほんの少し渉猟してみたのですが、当時見たコラムが、見つかるわけもありませんでした。もっとも、永山則夫が永山則夫連続射殺事件を起こしたのは1968年11月~1969年4月で、この時私は15歳ですから、時期は符合しますので、私の記憶がまるで根拠がないということはなさそうです。とはいうものの、永山則夫は2か月にも満たない間に、東京、京都、北海道、愛知と日本の各地を転々として殺人を繰り返しており、寺山修司は、そうした永山則夫に対して、「地理的救済」という「言葉」を投げかけていたのだ、ということや、寺山修司と永山則夫の間には、書面のやり取りが、このコラムの後も、様々なかたちで続いていたらしいことなどは、分かっています。こうした複雑な関係も踏まえると、かなりの確率で、私のあの瞬間のうれしいひらめきは、的外れなものだったのではないかとも思います。しかしそれでも私は、当時の私の心境の変化をも包み込んでくれるような適切な「言葉」を与えてくれた寺山修司という詩人に、心から感謝しています。
「国語」という教科との付き合い方
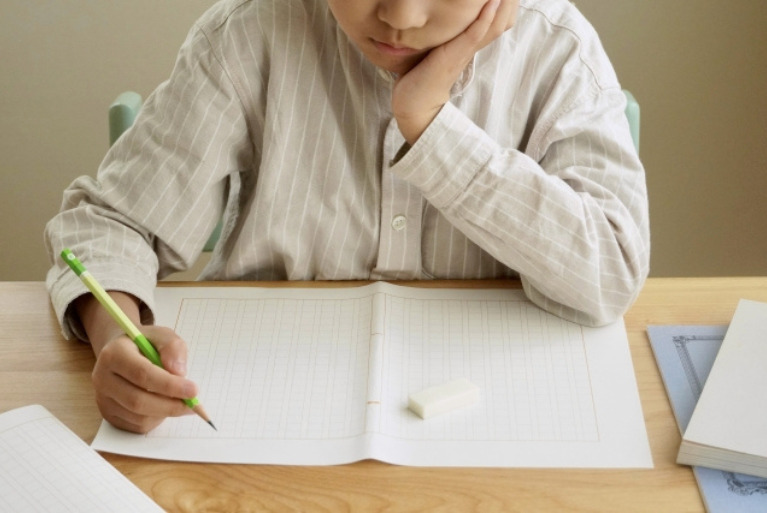
中学2年生の頃だったと思います。「同胞」という二文字熟語の読みが、国語のテストに出ました。私は、普通の「どうほう」という読み方も知っていたのですが、ほんの少し前に、分かりもしないのに、「ファウスト」の「第二部」の字面を追っていたことがあり、そこに「はらから」というルビが振られていたので、「きっとこの読み方の方が格調が高い読み方なのだろう。」などと考え、答案用紙に「はらから」と書いて、バツのついた答案用紙を返されました。先生に抗議したのですが、「あれは当て字だから、絶対に正解にはできない。」と、抗議はかたくなに拒否されてしまいました。「おかしい。」と思いましたが、一方、「多分、自分をアピールする場ではないところで、必要のないアピールをしたのが、まずかったのだろうな。」という考えも、漠然とではありますが、頭の片隅には生じていました。
また、私は、日本の小学校や中学校や高校の「国語」に、とてつもなく大きな特質があることが気になってくるようになっていました。日本の「国語」ですから、授業の素材は、当然「日本語」なのですが、しかし、「国語」という教科には、「日本語」を使ってコミュニケーションのスキルを磨くといった「日本語」を道具として使いこなすことを習熟させる観点が、ほとんど完全に興味や関心の埒外に追いやられており、その代わり、日本の学校教育の中で、「国語」はもっぱら情操教育の一環と位置付けられて、「日本語」は、何よりもまず観賞の対象として取り扱われているということに気が付いたのです。ですから、「日本語」は「国語」という教科の中では、美術や音楽や道徳といった極めて主観的な科目と同じような視点から、吟味されるということになってしまいます。まさにこのことこそが、日本の「国語」という教科、あるいは「国語教育」の特質なのではないかと、いつかは忘れたものの、私は、ある時から薄々感じるようになり、それはやがて確信となっていきました。当初の私の思いからすれば、これは、日本の「国語」という教科の現状に対する批判として芽生えた一つの発見でした。そして、言語に対して、それをコミュニケーションのツールとして使いこなすという問題意識が希薄なことが、多分、「英語」にもネガティブな影響を及ぼし、何年学校で英語を教えてもらっても、まるで役に立たない、といったことになってしまうのではないか、などと漠然と考えていました。
しかし、私の「国語」観は、全く意想外のところで、大活躍してくれました。何と、「国語」のテストにどう取組むべきなのか、という難題に、この私の「国語」観は役立ったのです。私の「国語」という教科に対する考え方からすれば、「国語」が素材としている「日本語」は、芸術や道徳の対象であるわけですから、「絶対にこれが正しい。」「これは明らかに間違っている。」といった白黒をはっきりさせるような断言のし方は、どちらかと言えば不向きです。好みの問題だったり、イデオロギーの問題だったり、いろいろな要素が絡み合うわけですから、解は多岐なものとならざるを得ません。そこで私は、「『国語』のテストに、客観的な正解はない。そこにあるのは出題者の『思い』だけだ。」と考えたらどうだろうと思いつきました。すると、「国語」のテストで高い点をとるには、出題された文章の選ばれ方、設問自体の内容、設問の配列、択一式の設問ならその組み立てなど、「問題」から読み取ることができるあらゆる情報を収集し、分析して、出題者の「これが正解だ。」という「思い」を汲み取り、こうして推察された「思い」に依拠し、そしてもう一つ忘れてはならないポイントですが、おのれを虚しくして、解答していくのが、最も「正解」と評価されるものに辿り着く率が高い方法だ、ということになります。少し言い方を変えると、いきなり、「正解」を考えるのでなく、「問題の作り方」からその「問題」が何を「正解」とするつもりで作られたものなのかを探っていく方法が、唯一の解決策ではないかと考えたのです。この「国語」のテストに対する対応策は、実際、とても有効でした。国語のテストの点数は、標本分散が小さいので、とびぬけた高得点をとると、偏差値は、びっくりするほど高いものとなります。私は、数学や英語で満点を取っても絶対にとれないような高い偏差値を、国語で結構取っていました。「同胞」の2つの読み方のどちらをとるかも、この観点からすれば、迷いようのないことだったわけです。
学生時代、勉強が良くできた方に、中学や高校の時代の「国語」のテストの結果をたずねると、「他の科目の場合と違って、当たりはずれが多かった。」といった答えを良く聞きます。私の考えでは、このような方々は、自分の考えで「国語」のテストを解いたので、出題者の考えと合った時に「当たり」となり、合わなかった時に「はずれ」となったのだと思います。こうした方々は、主体性という意味では、むしろ正しい生き方を通しておいでなのだということなのかもしれませんが、私の考えによれば、「国語」という教科との付き合い方という点では、こうした生き方には不向きな面もあるということになるのではないかと思っています。
この私の「国語」観をもって、大学で経済学の勉強をするようになったところ、「えっ!?」と驚くしかないことに出合いました。大学でケインズの「証券投資は、美女選びというよくある新聞の懸賞と同じだ。」という考え方を知り、私の国語のテストへの対処のし方は、こうしたケインズの例え話とかなり本質的なところで通じるところがあるのではないかと思ったのです。ケインズは、こんな風に説明しています。
「専門投資家は、百人の写真から最高の美女六人を選ぶといった、ありがちな新聞の懸賞になぞらえることができます。賞をもらえるのは、その投票した人全体の平均的な嗜好に一番近い人を選んだ人物です。したがって、それぞれの参加者は、自分が一番美人だと思う顔を選ぶのではなく、他の参加者たちが良いと思う見込みが高い顔を選ばねばならず…」(雇用、利子、お金の一般理論、ジョン・メナード・ケインズ著、山形浩正訳、講談社学術文庫225ページ)
もちろん、私の国語観は、ケインズの議論と全く同じものではありません。しかし、「自分というものがあっても意味はない、むしろ他者がどう考えているのかを推し測ることこそが意味があることなのだ。」というところはほとんど同じなので、悪い気はしませんでした。
この私の「国語」観に関わる話は、弁護士になってある弁護士の友人を持ってから、また、少し広がりができました。この友人の弁護士は、某有名私大の航空機学科の出身者で、ずいぶん早い時期からパソコンが大好きな人だったのですが、コンピューター・ゲームも大好きで、中でも「信長の野望」や「三国志」といった歴史シミュレーションゲームを始めると、文字通り寝食を忘れてのめり込み、それを「ゴール」と言うのでしょうか、最後には、いつも必ず、最高得点のステージまで到達してしまうのです。どのゲームも征服してしまうので、やはり共通の友人の弁護士が、「どうやるのか?」と思わず質問しました。そこで、返ってきた答えが、「自分がどうやろうか、などという考えは、はなから捨ててかからなければいけない。まず、試行錯誤をして、ゲームを作った人の『どうするとどうなる』という『設計者の考え方』の推定を、徹底的にやる。『設計者の考え方』さえ分れば、それに合致した対応をしていくだけだ。そうすれば、必ずゴールにたどり着ける。」というものでした。シミュレーションゲームの場合、「設計者の考え方」と、「国語」の出題者の「思い」とは、同じものであるはすがありません。もちろん、推理のやり方も全然違います。それでも、「シミュレーションゲームの、一つひとつの場面は、どの選択がゴールに至るものか、といった『正解』をゲームをしている人の価値観で見付けようとしても、意味はない。『正解』を知るための唯一の道は、設計者の『ゲームの製作の了簡』を探り当てることである。」といった考え方に、発想において、私の「国語」観と一脈通じるところがあるような気がして、とても興味深く思いました。
唯名論と実在論
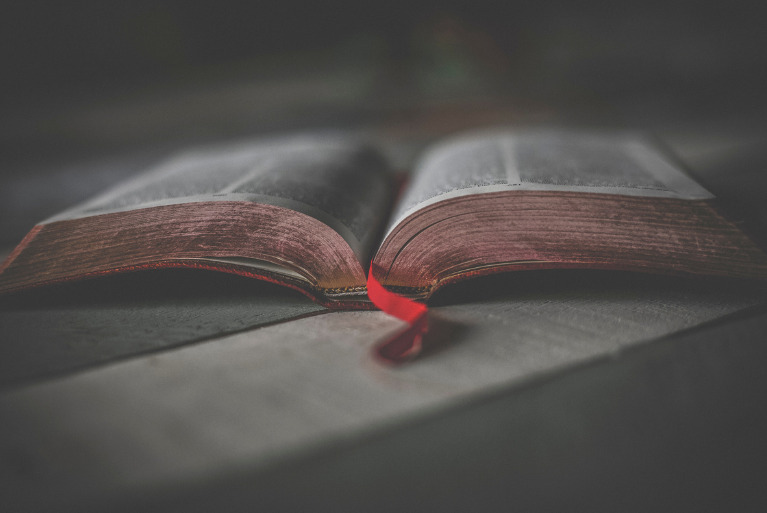
唯名論と実在論、あるいは、唯名論的なものの見方と実在論的なものの見方は、ヨーロッパ中世のスコラ哲学に生じた気の迷いなどではありません。それどころか、唯名論と実在論、あるいは、唯名論的なものの見方と実在論的なものの見方は、人類にとって、その初めから終わりまでの全てに通じる「物事のみかた」、「物事の整理のしかた」の本質的な対立の一つであり、しかも、その中でも最も重要なものであると、私は、常々、考え続けてきました。この小文は、常日頃から気になっていながらも、自分自身の言葉だけでは、なかなか考えをまとめきれなかった、この「唯名論」と「実在論」を、専門家の論稿の一部を引用させていただくことで、自分の理解の不十分さを補わせていただきながら、なんとか、まとめてみようと試みたものです。そして、せっかくですので、「分節」という、関連するカテゴリーについても一瞥し、応用的なことにも考えを進めてみました。
「普遍論争」そのものについては、山内志朗著 平凡社ライブラリー「近代の源流としての普遍論争」の20~22ページの引用で、説明にかえさせていただきます。
「唯名論」と「実在論」は、中世の「スコラ哲学」における最大の論争だった「普遍論争」と呼ばれる論争における二つの対立する、絶対に相いれない立場であって、発端はポルフュリオスの『イサゴーゲー』(アリストテレス、カテゴリー論入門)の一節にあるとされています。そこには次のように書かれています。
例えば、まず第一に類と種に関して、それが客観的に存在するのか、それとも単に虚しい観念としてのみあるのか、また存在するとしても、物体であるのか、非物体的なものであるのか、また[非物体的なものであるならば]離在可能なものなのか、それとも感覚対象の内に、これらに依存しつつ存在するのか、という問題については回避することにする。
ポルフュリオスがここで答えを出さなかったから、中世の哲学者は普遍について議論を重ねたといわれることもあります。そして、中世哲学全体を貫く最も重大な問題は「普遍」の実在性の問題であり、スコラ哲学はそれと共に始まり、それと共に終わった、と述べられたりもします。
この普遍がどう捉えられるかについては、中世哲学において、様々な見解が出され、激しく論議されたものですが、通説によると大きく分けて三つになるとされています。実在論、概念論、唯名論というようにです。
実在論(realism)とは、普遍とはもの(res)であり、実在すると考える立場で、換言すれば、普遍は個物に先立って(ante rem)存在する、と考える立場とされます。…
唯名論(nominalism)は、普遍は実在ではなく、名称(nomen)でしかない、したがって普遍はものの後(post rem)にあるとするものです。個々の人間は触ったり触れたりできますが、普遍としての人間は感覚可能ではなく、触ることも見ることも酒を飲ませることもできません。…
概念論(conceptualism)というのは、実在論と唯名論の中間に来るもので、普遍とは個物から独立に、そして個物に先立って存在するものでもなく、ものの内(in re)に存在し、思惟の結果、人間知性の内に概念として存すると考える立場です。…(本稿では、概念論は取り上げません。)
このように整理しますと、
「実在論―個物の前(ante rem)」、
「概念論―個物の中(in re)」、
「唯名論―個物の後(post rem)」
という図式を手に入れることができます。
というわけです。高度に抽象的な用語の間に「前」、「後」という日常用語が挟まっており、違和感を感じられるかもしれませんが、これは、人間の認識は、後先、順序、流れ、総じて時間というベクトルから自由になれないものだということが、所与の前提になっていることから生じた、ほかには表現のしようのない言葉遣いだと理解していただければと思います。
こうした「普遍論争」というヨーロッパ中世の伝統を背景として、現代の言語哲学、論理学の分野にも、知の巨人たちが登場します。その中でも、現代の言語学(言語哲学)を語る上で最高の大立者がフェルディナン・ド・ソシュールでした。私にとってソシュールのことを教えてくれた恩人は、丸山圭三郎ですが、ソシュールの「唯名論」への直接的な言及については、フランソワーズ・ガデ著 立川健二訳 ソシュール言語学入門 56ページを引用させていただきます。
言語(ラング)を定義しようと試み、何が言語を構成しているかを問題にすることによって、ソシュールは、なによりも否定的な主張にたどりつく。言語を名称目録(ノマンクラチュ-ル)として考えることはできない。というのだ。言語は、ある事物とそれを指し示す用語(テルム)との絆によっては定義されないのだ。そこでソシュールは、言語を「同数の事物に対応する用語のリスト」…と見なすような言語観に対して最初から反対の立場をとる。そのような言語観では、一揃いのレッテルをつうじて指し示されることを待っている、事物(ないし観念)のストックを想定してしまうことになる。だとすれば、表現すべき概念(事物ないし概念)は言語以前にすでに構成されており、その仲介なしでも考えられるということになってしまう。それにたいして、ソシュールはつぎのような表象を対置している。「それ自体においてとらえると、思考は星雲のようなものであって、そのなかで必然的に画定されているものはひとつもない。あらかじめ確立された観念は存在せず、言語の出現以前には、なにひとつ分明(ディスタンクト)なものはない」…
ソシュールは、「普遍論争」において、非常に明確に「唯名論」の立場に立って、「実在論」を否定していることが分かると思います。
ソシュールの言語哲学の場合、言語の機能を語る際に、非常にしばしば、「分節」という用語が用いられています。「分節」という言葉は、ソシュールによって使用されるようになった時までは、「全体をいくつかの区切りに分けること。また、その区切り。」といった一般的な言葉に過ぎず、取り立てて、哲学的な意味を付されたものではありませんでした。しかし、ソシュールは、この言葉にとても深い意味を持たせ、意識して自らの理論の重要な術語の一つとして使いました。こうして、「分節」という用語は、「差異」いう用語と一対になって、「記号学」の出発点としての重要な役割を果たす概念とされることになりました。
この「分節」については、石田英敬著 ちくま学芸文庫「記号論講義」(81頁以下)を引用させていただきます。
「現代の記号理論の出発点になったのは、ソシュールにおいても…『分節』という考え方でした。『分節(articles)』とは差異によって区切られた単位…をいいます。…分節が示しているのは差異に基づくシステムという原理です。ここで重要なのは、分節は差異に基づく構成単位であ…るということです。」
それまで何の境目もなかったところに、同じ意味、同じ価値を持っているまとまりを選び出し、それ以外のものと区別した場合、同じ意味、同じ価値を持つもののまとまりのことを「分節」といいます。選ぶために用いられる道具は、さしあたり言語をその代表格とする記号ということになります。つまり言語などの記号を使って「分節」が行われる前には、「分節」が行われる対象としての世界には、どこにも意味や価値のまとまりはありません。「分節」という操作の結果として、初めて、「唯名論」に言うところの「名」の対象の範囲が定まることになります。したがって、ソシュールが使用した「分節」というプロセスは、まさに、「唯名論」の分析的説明に他ならないものなのです。
次に、「普遍論争」に対して、複雑な姿勢を貫いた大言語哲学者ルートウィヒ・ウィトゲンシュタインについてみてみたいと思います。ウィトゲンシュタインについては、藤本隆著 講談社学術文庫 ウィトゲンシュタイン 174~175頁を引用させていただきます。ウィトゲンシュタインには、前期の考え方と後期の考え方の区別があり、前期の考え方は、転向といわれることもあるほどの激烈さで根本的に変更され、後期の考え方を展開させた哲学者でした。
まず、語られるのは「前期ウィトゲンシュタイン」です。
フレーゲやラッセルの「新しい論理学」を学んだ若きウィトゲンシュタインは、一方では像が論理的に許される範囲(論理空間)を厳密に限定しようとして、比較的容易に真理表や命題の一般形式を発見したのですが、しかし、他方ではそのように許容された像の真偽決定問題に縫着し、やや無反省に伝統的な真理の対応説に準拠して、像の特殊例たる「写像Abbild」概念を導入してしまいました。すなわち、言語の経験的有意味性の根拠を事実の写し絵たることに求め、命題の論理形式が、それに対応しているはずの現実の形式と同一であることこそ(つまり、論理的に分析された命題の諸要素が世界内の特定の対象を指示していることこそ)、当の命題の真理性を保証してくれるのだ、と考えてしまったのです。かくしていわゆる「写像理論 picture theory」は、のちに「論理的原子論 logical atomism」と呼ばれるようになったラッセルの実在論世界解釈とともに、しばらくの間伝統的な対応論を論理的に精緻なものにしたと考えられ、論理実証主義者をはじめとする科学哲学者たちに広く受け容れられたのでした。
ここで「前期ウィトゲンシュタイン」が論じていたのは、「実在論」そのものでした。しかし、「後期ウィトゲンシュタイン」言語についてのものの考え方は、以下のように、様相が一変します。
しかし、ウィトゲンシュタインは、『論考』刊行後十年たらずの間に、そのような写像概念が実は空虚な論理学的要請にすぎないこと、言語の有意味性を実在世界との対応関係によって保証することなどできないことに気がつきました。。後年(1932年7月1日)かれはワイスマンに向って「『論考』ではわたしは論理分析と直示的説明について不明確だった。わたしは当時、<言語と現実との結合>が存在する、と考えていたのである。」と述べ、結局は「旧著の中で書いたことのうちに重大な誤りのあることを認めなくてはならなくな」ったのでした(『探究』序文)。
たとえば、「水!」「あっち!」「だめ!」といった表現は、それぞれ論理分析を行ってその論理形式を確定することなどできないような表現なのだけれども、だからといって、このような表現がわれわれの現実生活の中で無意味になってしまうわけではない。むしろ逆に、このような警告とか命令とか禁止とかの表現は、人間の生活を維持していくために不可欠の役割を果たしている。『探究』のウィトゲンシュタインは、人間生活の中で行われるそのような言語の働きに注意し、言語の意味を「言語ゲーム」という活動の中で杷え直そうとする。ことばは、それに対応する客観的な現実世界のありさまによって意味を決められるのではなく、それを使う人間の生活様式の中でそれが果す役割によって意味が決まる。「語の意味とは、〔たいていの場合〕言語内でのその慣用である」(『探究』第一部第四三節)。
このように、後期のウィトゲンシュタインは、明らかに「実在論」を捨てました。もっとも、後期のウィトゲンシュタインは、言語に対する視座を「人は言語を使って何をしたいのか。」、「人にとって言語にはどんな利用価値があるのか。」というところに置きましたが、こうした言語は何のためにあるのかについての価値判断は、普遍論争の論客たちすべてが共有していた言語観とは異なっています。そこで、後期のウィトゲンシュタインは、「実在論」を捨てたからといって「唯名論」の立場に立ったと明言できないところはあります。しかし、普遍論争から導き出された「図式」からすると、後期のウィトゲンシュタインのとった立場は、明らかに「個物の後(post rem)」なので、後期のウィトゲンシュタインの立場は、「唯名論」だったといって間違えではないと思います。
この「転向」を無視して、「前期ウィトゲンシュタイン」だけでウィトゲンシュタインを語ろうとする人もいるようですが、こうした理解は、ウィトゲンシュタインについての正しい理解だとは思えません。ウィトゲンシュタインは、「前期」の理論が誤っていたと気が付いたからこそ、「後期」の理論の中に足を踏み入れたのです。もっと端的に言えば、はじめは、「実在論」が真理だと思っていたが、のちにその考えの過ちに気付き、「実在論」ではないもの、どちらかといえば「唯名論」に近いものこそが真理だと考えを変えたということなのだと思います。
私は、個人的には、「唯名論」の信奉者なのですが、普遍論争、とりわけ実在論と唯名論の対立は、現代社会においても、人間の言語活動を通した、世界とのかかわりや感じ方についての二項対立、人間がおちいりやすい世界とのかかわりについての実感についての2つの典型的な類型だと思っています。そこで、どんな新しい「発想」に接した場合においても、あるいは古くから知られている「発想」の理解を深めようとするときにも、私としては、向かい合うことになった「発想」を、実在論と唯名論の二項対立に対比させることから始めることとしています。そして、この対比は、いつも、物事に接するに際して、座標軸として、有効な機能を発揮してくれる、と私は感じているのです。
実在論と唯名論の二項対立に対比させて、特定の考え方の「発想」を吟味すると、どんなことを知ることができるか、関連した問題に簡単に触れてみようと思います。
科学哲学・論理実証主義、あるいは、一般に科学といわれているものの信望者は、前期ウィトゲンシュタインを歓喜をもって迎え入れました。前期ウィトゲンシュタインの写像理論は、ウィーン学派と呼ばれる論理実証主義のグループに圧倒的に受け入れられ、現代の科学の哲学的基盤を構築したといわれています。
科学哲学・論理実証主義では、客観的な世界がまず実在していることを疑わない、という、信仰告白から話は始まります。そして、その客観的な世界を知るための仮説が(数学も含めた)言語という道具を使って打ち立てられ、この仮説にエヴィデンスが加わると、仮説は真実に格上げされ、それまで存在していたけれども知ることのできなかった真実が明らかになったとされるということのようです。エヴィデンスは、普遍と個物の「対応」の確認であり、対応が確認できなければ、全ての知的営為は意味をなさないことになってしまうことから、科学哲学は、結果的には、エヴィデンス至上主義といった様相を示すことになっているように思われます。
このように、科学哲学・論理実証主義は、一見すると、閉じた系で、その内部は緻密な構成とされ、どこにも隙がないかのごとくですが、少し考えても、いくつかの例外に思い至ります。例えばそれは以下のようなものです。
① カール・ポッパーの反証可能性という議論からすると、どんな科学的命題、あるいは、科学的カテゴリーも、すべて真実でないかもしれないという可能性を背負わされており、そうした科学的命題や科学的カテゴリーを使っても、そこに形成されうる「分節」は、全て暫定的なものでしかなく、安定的に世界を「分節」していくことは、一切できないということになってしまう(カール・ポッパー 科学的発見の論理(上) 大内義一・森博嗣 訳 95頁以下)。
② 本来、科学が対象としなければならない事象の中に、統計学という考え方(過去と将来を対比して、両者の関係性を前提として、前者の分析から後者についての何らかの意味のある事柄を見つけ出すことができるという考え方で、カール・ポッパーが、「歴史主義の貧困」の中で批判し尽くそうとした発想なのではないかと思っています。)を取り入れないと、説明できないものがある。
③ 前記②と似たところがあるが、現代の最先端の物理学に不可欠な、確率という考え方も、すんなりと科学に取り入れることは出来ないという議論がある(カール・ポッパー 科学的発見の論理(上) 大内義一・森博嗣 訳 184ページ以下)。
④ 医学においては、その性質上、エヴィデンスを示すことなどは、およそ考えられないにもかかわらず、明らかに観察される現象について、「学問的説明」の場でも、しばしば、それは、「目的的に進行してきた進化の結果なのだから、肯定し、受け入れるべきだ。」と進化論でかたづけられてしまう。
こうした、あらさがしをすると、科学も、見方によっては、それほど盤石なものではない、ということが、お判りいただけたでしょうか。
話題をガラッと変え、以下においては、「普遍論争」の観点から、陰謀論(コンスピラシー・セオリー)を論じてみようと思います。
それはこのようなことになります。アメリカのジャーナリストのマイケル・バーカンによれば、陰謀論は、「何事にも偶然はない。」、「何事も表面とは異なる。」、「何事も結託している。」の三つの原則から成るものだとしています(田中聡著 幻冬舎新書陰謀論の正体!73ページ)。この場合、「表面とはことなる何か」・「結託している何か」は「個別の偶然ではない事件」に先立って存在しており、「個別の偶然ではない事件」は、「表面とはことなる何か」・「結託している何か」の仕業であると結び付けられることによって、その存在の説明が完結するのです。「個別の偶然ではない事件」に、すぐに、納得感のある「表面でない何か」・「結託している何か」が見つからない場合は、何としても探し出そうとするし、そうしないではいられないのです。極論するなら、それはこじつけでも構いません。
こうした陰謀論の思考形態は、明らかに実在論的な構造を内在しています。ですから、陰謀論が好きな人は、実在論者であることが多いであろうし、唯名論的な傾向の人は、陰謀論に対して違和感を持つことが多いということができるのです。