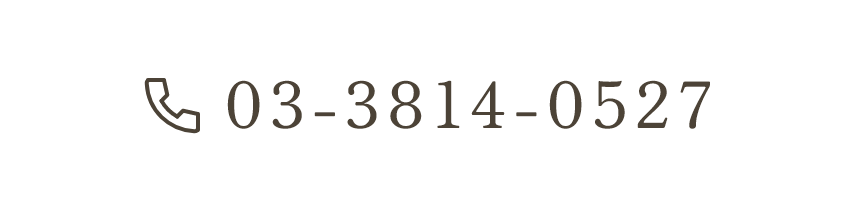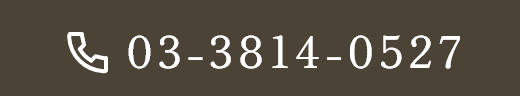要件事実の黎明―立証責任論論争の時代から要件事実の時代へ―

日本の民事法の分野にも、古くから立証責任の議論はあったようですが、「昭和四十年代に入って噴出してきた多くの現代型訴訟―公害、自動車事故、医療事故、製造物責任などの訴訟に」それまでの学説(旧規範説)では「必ずしも十分に対処しえない」(石田穣 『証拠法の再構成』 東京大学出版会 1980年6月10日刊 49頁)という事態が、問題として意識されるようになったということのようです。こうした状況を背景として、1970年代の初頭のころから石田穣先生が当時の通説であった旧規範説の痛烈な批判をはじめ(石田 前掲書 54頁)、これに対して、石田先生以外のほとんどすべての先生方が、旧規範説を、ローゼンベルクが『立証責任論』(倉田卓司訳 判例タイムズ社 1972年 4月28日刊)などで展開した「法律要件分類説」などで補強して修正規範説とでも呼ぶべきものに仕立て上げ、両者の間で「立証責任論論争」が繰り広げられました。もっとも、当時の裁判官は、おおらかで、柔軟な発想をお持ちだったという印象があります。私にとって日本の判決の中で最も格調の高いものの一つだと常々思っている「新潟水俣病」の地裁判決は次ように判示しています。「以上からすると、本件のような化学公害事件においては、被害者に対し自然科学的な解明までを求めることは、不法行為制度の根幹をなしている公平の見地からして相当ではなく、前記1 (原因物質)、2(汚染経路)については、その状況証拠の積み重ねにより、関係諸科学との関連においても矛盾なく説明ができれば、法的因果関係の面ではその証明があったものとすべきであり、右程度の1,2の立証がなされて、汚染源の追及がいわば企業の門前にまで到達した場合、3(加害企業における原因物質の排出)については、むしろ企業側において、自己の工場が汚染源になりえない所以を証明しない限り、その存在を事実上推認され、その結果全ての法的因果関係が立証されたものと解すべきである。」(新潟池判昭46・9・29,下民集22巻9・10号別冊1頁)。この判決で論じられている立証責任の議論は、修正規範説でも説明できるものなのかもしれません。しかし、この判決の立証責任論は、私のみるところ、立証責任論論争の文脈の中では、石田説に近いものなのではないかと思われます。
立証責任論論争の中で修正規範説をとる先生方が最も頼りにしたのがローゼンベルクだったわけですが、ローゼンベルクの『立証責任論』(前掲書)は、単なる主張立証責任の分配の次元にとどまるものではありませんでした。ローゼンベルクの場合、主張立証責任の問題は要件事実を媒介にしてのみ論じることができるものとされていたからです。ローゼンベルクは、このように論じて、読者に注意をうながしています。「しかし、凡俗的な見解は、法規を権利の発生や障害等の原因として見ることをせず、むしろ法規の構成要件をなす事実に直接戻って、これがため権利が発生したとか、その存在ぶりが変わったとか考えてしまうのである。…(しかしながら)…事実なるものは決してそれ自体で法律関係に作用しうるわけではなく、法規に基づいて然るのであり、法規の要件を含んだり、これを認識させたりする限りにおいてのみ意義を有するのだ、ということを忘れてはならない。したがって、ある事実が拠権・障権・滅権・排権のいずれに属するかの問に答えるに当っては、その事実を要件としている法規に常に立ち戻らねばならぬ。」(ローゼンベルク 前掲書 122頁以下)引用したところには、「『むき出しの事実そのもの』と『要件事実』との峻別の必要性」についてのローゼンベルクの考え方も表明されていますし、また後半では、ローゼンベルクの学説が「法律要件分類説」と呼ばれる所以を知ることができ興味深いところです。私の印象からすると、ローゼンベルクの場合、要件事実についての議論のほうが主張立証責任についての議論より前に所与のものとして確立しており、前掲書の中の主張立証責任についての議論は、すでに確立されていた要件事実の問題についての議論の基盤の上に立って展開されているという感じがします。しかし、今から約半世紀前の日本では、とりあえず主張立証責任の問題のほうだけに関心が集中し、というか主張立証責任の問題で手いっぱいで、立証責任論論争に、要件事実の問題についての議論を包摂させるまでには至っていないようでした。事実、石田先生の『証拠法の再構成』(前掲書)という論文集の巻末の索引には「要件事実」という項目も無ければ、「法律要件」という項目もありません。また同じく石田先生の『法解釈学の方法』(石田穣 法解釈学の方法 青林書院新社 1976年7月20日刊)という論文集の巻末の索引にも「要件事実」という項目は存在せず、「法律要件」という項目はあるにはあるのですが、意味するところが今の用語法とは全く違います。他方、倉田卓司先生も「ローゼンベルクの『証明責任論』を訳しながら、わが民法の教科書の叙述に要件事実的感覚が少ないのに気付いて驚き、要件ごとに証明責任を明示した本があったら、と夢想した…」と述懐(倉田卓司監修 『要件事実の証明責任 債権総論』 西神田編集室 1986年刊 (序の部分の)1頁)しておられます。こうしたことから推察できると思われるのですが、立証責任論論争が華やかに行われていたころの日本の民事法学会では、まだ、要件事実の問題は、当事者たちの関心の中心とはなってはいなかったということのようなのです。
このようなバックグラウンドの中で、さしあたって立証責任論の分野でということではあったのですが、石田説はローゼンベルクの法律要件分類説に大きな影響を受けた修正規範説に完敗しました。以後、石田先生の学説は、残念なことに、すべての分野において、少数説としての存在すら認められず、「無視」され続けることになってしまいました。その結果何が起こったかはあきらかです。日本の民事法学会は、ローゼンベルクの学説によって席巻されることになったのです。
もちろん、こうしたことをきっかけとしながら、ローゼンベルクの学説は、日本の民事法学会において、内在的に、しかもより深く受け容れられていくことになったのだと思われます。そうなれば、立証責任論にとどまらず、ローゼンベルクが、立証責任の議論の当然の前提と考えていた「要件事実」にかかわる考え方も、日本の法律家の間で、理解が深まり、受け容れられていくことになったのでしょう。石田先生のような批判勢力は既に事実上不在という環境にあったわけですから、日本の民事法学会では、「要件事実」についても、その内容(構造)や必要性の根拠や適用すべき(し得る)範囲になどについて、ローゼンベルクの考え方が一気に広がっていったのは必至のことだったのだと思われます。こう言った事態の推移からすれば、いつからかははっきりとは分かりませんが、必ずしも2004年の法科大学院(日本版ロースクール)の創設を待つまでもなく、「要件事実」が裁判実務の中心として君臨する時代がやってくるのは、時間の問題だったということなのだと思われます。
「要件事実」論と概念法学

私が司法研修所に在籍していた1981年ころ、10人いた民事裁判の教官の内、口を開くと「要件事実」の話になることで有名な教官は一人だけしかおいでになりませんでした。当時、このユニークな教官は、ほとんどすべての修習生から奇人変人として敬して遠ざけられていました。この時代は、立証責任論論争の末期だったはずですので、まだ「要件事実」が関心の中心となる時代には入っていなかったのだと思います。事実、日本の要件事実論の隆盛にとって記念碑的な著書というべき「司法研修所民事裁判教官室編 民事訴訟における要件事実 第一巻」は、第1版第1冊が1985年8月15日に発行されています。また、1986年7月15日に西神田編集室から刊行された「要件事実の証明責任 債権総論」の「はしがき」で倉田卓司先生は「ローゼンベルクの『証明責任論』を訳しながら、わが民法の教科書の叙述に要件事実的感覚が少ないのに気付いて驚き、要件ごとに証明責任を明示した本があったら、と夢想した…」と述懐しておられます。こうしたことからもお分かりいただけるように、私は「要件事実」について特別な教育を受けた世代ではありません。ですから、お世辞にも「要件事実」という事実を法律に効果的に結びつけるための方法論を自由に使いこなすスキルを持っているなどとは言えませんし、はっきり言ってものすごく不得意です。もっとも、私も、弁護士を生業としている以上、「要件事実」は、今日の裁判実務では、避けて通ることのできない素養の一つですので、好んでそうしているというわけではありませんが、日々それなりの努力を積み重ねて精進しているつもりではいます。確かに「要件事実」を意識して事案、とくに原被告双方の主張の整理をすると、夾雑物をふるいにかけることができるせいか、それまではっきりしなかったことが見えてくるという実感を持ったことも何度となくありました。
このように、錯綜した事実を整理して呈示するときなどにはとても便利な「要件事実」ではあるのですが、「度が過ぎた使われ方」をされるようになると、様々な弊害が目立つようになって来るように私には思われます。そのような、弊害はどうやら避けられないもののようなのですが、避けられない理由は何なのだろうと戸惑うようになりました。そんな中でふと頭をよぎったのが、「もしかしたら、『概念法学』との、いささか時代遅れの蜜月こそが、『要件事実」に内在している問題の根源に横たわっているものなのかもしれない。」ということでした。
「概念法学 Begriffsjurisprudenz」と「自由法論 Freirechtslehre」の二つの考え方、それだけを呈示して「法律の解釈の方法論としてどちらの立場に立つか。」という問いを発したとすれば、現代の法律家の中に、「概念法学」とストレートに答える人は、まずいないと思います。ほとんどすべての人が、若干のためらいは見せるかもしれませんが、「自由法論」と答えるでしょう。「概念法学」は、「成文法万能主義」をとり、「制定されている法律は、論理的に完全で欠陥がないから、適切な論理操作がなされれば、あらゆる問題について解決にたどり着くことができる」という信念(法秩序の論理的自足性logische Geschlossenheit der Rechtsordnung というのだそうです。)のことをいうわけですが、人間が作った法律には、立法者が想定していなかった事態に対処するための規範は書き込まれていないのですから、このような制定法の不完全性(「法律の欠缺Luecken im Recht」という用語で表現します。法に内在するこうした構造は、エールリッヒによって重視され、その存在が強調されました。例えば『法社会学の基礎理論』(河上倫逸他訳 みすず書房 1984年5月10日刊)419-421ページを参照)を正面から認めたうえで、司法を信頼して、裁判官の自由な「法創造」に委ねることによってこれを補おうというのが「自由法論」です。こうした自由法論の考え方を象徴的に具体化したものとして有名なのが、「この法律に規定がないときは裁判官は慣習法に従い、慣習法もないときには自己が立法者であったならば法規として制定するであろうところに従って裁判すべきものとする。」という「スイス民法典第1条第2項」の条文です。(ここで論じた問題は、本当は、もっと複雑なようです。団藤重光 法学の基礎〔第2版〕 2007年5月10日刊 247ページ以下、とりわけ、「概念法学」については305ページ以下、「自由法論」については308ページ以下を参照してみてください。)
一方、最近の裁判所が極端なまでに重用している「要件事実」は、「この裁判規範としての」制定法「の要件に該当する具体的事実」(伊藤滋夫 『新版要件事実の基礎』 有斐閣 2015年6月25日刊 3ページ)と定義されています。ということは、制定法が存在するところに、初めて「要件事実」が存在しうることになるし、逆に言えば制定法がなければ、「要件事実」も存在しえないということになるわけです。しかし、「民事判決における判断は、…いろいろな要件事実の存否についての判断を組み合わせて行われるものである」(伊藤滋夫 前掲書 13ページ)とされていることから、「要件事実」はすべてを網羅していることがアプリオリに前提とされていること、言葉を変えていえば「法の欠缺」の存在が無視されている、あるいは、法には欠缺など存在しようがないと言う公理が初めからドグマとしてまつりあげられていることがわかります。というのも、この「民事判決における判断」の伊藤先生の説明は、判断できない場合があること(あるいは、自由な裁判官によるスイス民法典第1条第2項に基づく判断以外に判断のしようがない場合があるということ)の存在を全く視野に入れていないからです。すると、このことは、とりもなおさず、その基礎をなしている「制定法」がすべてを網羅していることを意味せざるを得ないということになるでしょう。「制定法」についてのこのような発想は「概念法学」そのものです。
何が問題なのかは今や明らかかと思います。「要件事実」で「制定法」を説明し尽くそうという理論(以下「要件事実万能論」といいます。)は、制定法が不完全なものなのだという、「自由法論」が到達した真理から、目をそらそうとします。こうなってしまうと、「要件事実」は、便利なものから有害なものに変質してしまうしかありません。要件事実万能論を信奉する法律家は、「法は完全無欠のものではない。だから物事の真の姿を見ようとするときには、時として制定法や要件事実の用語法や体系から離れなければならないこともある。」という、私にしてみれば当たり前の真理を認めるという発想が欠如しているため、現実から遊離したり、現実から目を背けてしまったり、現実を見る目が深まらなかったりしてしまうような気がするのです。考えてみれば、こうした問題意識は、「自由法論」が「概念法学」に対して持った問題意識と同じものです。「時代の歯車が逆転しているのだろうか。」私は、時に、そんな暗い気分に陥ることがあります。
「要件事実万能論」と「混合契約」

「要件事実」だけで、世界が説明し尽くせるといったこの「要件事実万能論」という考え方は、生きた「契約」を理解するのが極端に苦手なのではないか、そんな印象を私は持っています。というのも、「契約」というものの中には、もちろん、非常に定型的で、変化に対して保守的なものもありますが、近代社会が掲げる標語の一つに「契約自由の原則」があることを引き合いに出すまでもなく、一つひとつの契約にはその契約に独自の工夫が施されていることも多く、契約当事者間の利害状況を調整しようという努力の跡がにじみ出ているものも少なくないからです。また、場合によっては、そうした努力が実を結んで、全く新しい類型の「契約」が作り出されることもあり、その中には、その後、多くの人たちに使われるようになったものもありました。こうした生きた「契約」に対して、「要件事実」が持っているカードは、民法という制定法の中心の中に列記された「典型契約」だけです。制定法の中には、さまざまな特別法もあり、それぞれの特別法が、その立法理由に応じて、それまで野放しにされていた新規の「契約」に様々な制約を課したり、新たな機能を付与したりしているのですが、「要件事実万能論」の制定法に対する視座は、基本法の「契約」を解釈したり組み合わせたりして応用することが中心で、どちらかというと、こうした、特別法の中で具体化された「契約」の組み立てには、関心がないような印象が感じられます。「典型契約」と一応は言えそうなもののその中に含まれている制定法の文言からはみ出した約定や「非典型契約」の中の約定は、一般の法律家ならだれでも行う「反対解釈」などといった解釈技法の範囲を超えると、どう考えても「法律の欠缺」でしか説明できない領域に入り込んでしまう筈なのですが、「要件事実万能論」は、そうは考えません。「要件事実万能論」は、「概念法学」と同義であり、「制定法万能主義」を、そして、そうした考え方と裏腹の「『法律の欠缺』の不存在」を信念としているので、「典型契約」をはみ出す「契約」のバリエーションに対して、「典型契約」が用意することができる法律用語(要件事実)で説明し尽くそうとしますし、し尽くせると考えているのです。
これは想像に難くないことではありますが、「制定法万能主義」に立脚した「要件事実万能論」の立場に立つ法律家は、世の中で取り交わされたどんな契約についても、典型契約を当てはめることだけで説明しつくすことが可能だし、もしそこからはみ出す何かがあったとしても、それは「法」という秩序だった世界の外に位置する異物に過ぎないと考えているとしか思えません。ある契約に比較的近い典型契約があったとしましょう。こう言う場合「制定法万能主義(概念邦楽の立場)」に立脚した「要件事実万能論」の立場に立つ法律家は、しばしば、その契約の中に含まれている契約の当事者が苦心して作り上げた条項、別の言い方をすればその契約の個性的な部分を、夾雑物とでもみなしているのでしょうか、無視する傾向が非常に高いような印象を受けるのです。
もっとも、「非典型契約」の中には、1個の「典型契約」をモディファイすることによって説明をしつくすのでは不十分で、複数の「典型契約」を持ち出さないと、契約の全体像の説明が十分にできない場合もあります。「制定法万能主義」に立脚した「要件事実万能論」の立場に立つ法律家は、こうした契約のことを「混合契約」と呼んで複数の「典型契約」の束のように説明する立場をとることが多いようです。しかも、何個の「典型契約」でもよいので、これらを組み合わせるために「混合契約」という手法を使えば、この世の中のすべての契約を説明し尽くすことができるというのが「制定法万能主義」に立脚した「要件事実万能論」の立場に立つ法律家の確信のように思われます。
こうした見解は、しかし、「要件事実万能論」の立場に立つ法律家の、根拠のない思い込みだけに支えられているわけではないようです。というのも、そうした、私には「詭弁」としか思えない、このような考え方にもそれを支えるからくりが周到に用意されているからです。そうしたからくりの中で最も「いかがなものか」と思ってしまうのが、「準委任契約」という「典型契約」の恣意的濫用です。「準委任契約」という「典型契約」は、民法第656条にその制定法上の痕跡が示唆されていますが、そこには実質的内容など何もない場合がほとんどです。そこで、この「準委任契約」は、あえて名付けるとすれば「不得要領典型契約」とでも呼ぶべきものだと思います。この「不得要領典型契約」は、何にでもどこにでもいつでも使えるものなので、「混合契約」の説明に際して、適切な「典型契約」が見つからない時その隙間を埋めるのに最適な「典型契約」の1種として、重宝がられ、多用されているわけです。もっとも、この「準委任契約」という「典型契約」は、中身が何もない空虚なものなので、何かの契約について「それは、何々の『典型契約』と『準委任契約』が組み合わされた『混合契約』だ。」といったところでその契約について何の理解が深まるわけでもないこともまた言うまでもありません。結局のところ、「準委任契約」という要領を得ない契約(以下「不得要領典型契約」といいます。)で、隙間を埋めることによって作り上げられた「要件事実万能論」の世界は、「あらゆる契約は、『典型契約』か、いくつかの『典型契約』の組み合わせでその全体が説明できる。」という「要件事実万能論」にもとづく「制定法万能主義」主張に具体的な形を与えるという目的を実現するために行われているというだけのものに過ぎず、「準委任契約」という典型契約は、この目的の実現のためには、すこぶる便利な道具であるとはいうものの、空虚としか言いようのないものだということができると思います。
「フランチャイズ契約」の「要件事実」による説明

既存の「契約」を「要件事実万能論」に立脚し「混合契約」という便宜的道具を駆使して分析すると、その分析の結果が、まるで別異の「契約」に変身して再構築されてしまうことがあります。というよりそうなってしまうことの方が常態であるという気がします。たまたま、ある法律実務家がお書きになった「フランチャイズ契約」についての論述を拝見する機会がありましたので(弁護士K先生著『フランチャイズ契約裁判例の理論分析』 判例タイムズ社 2005年4月8日刊 14ページ)、このことを確認させていただくという意味も含めて、引用させていただくことにします。それはこのようなものでした。
「ビジネス・フォーマット型フランチャイズにおけるフランチャイズ契約の法的性質としては、
①フランチャイジーが商標(サービスマークを含む)及びノウハウのライセンスを受けるという点では賃貸借的要素がある。その他、
②フランチャイジーはフランチャイザーにより指定された一定の商品の販売およびサービスの提供を契約により義務付けられているという点でフランチャイザーを委任者と考えうる準委任的要素が認められ、また、
③フランチャイザーはフランチャイジーに対して使用許諾(ライセンス)をするノウハウについて継続的に改良・開発する義務を負い、その改良・開発されたノウハウを継続的に提供する義務を負い、またその改良・開発されたノウハウをフランチャイジーに伝達するために、フランチャイジー及びその従業員の訓練等を行うなどの経営に必要な指導・援助をすることが義務付けられるという点では、フランチャイジーを委任者と考えうる準委任的要素が弁護士Kある。そして、
④附随的な要素として、フランチャイジーがフランチャイザーから継続的に一定の商品や材料を購入するという点では、継続的売買の要素がある。したがって、フランチャイズ契約は、典型契約を基礎に考えると賃貸借的要素および準委任的要素を中心として、付随的に継続的売買の要素を含む継続的双務契約たる混合契約であると考えられる。」
このフランチャイズ契約の説明は、現在の代表的な「要件事実万能論」の大御所である加藤新太郎先生からも、
「著者(弁護士K先生)のフランチャイズ契約の要素に関する整理は、適切だと思いますね。」(『ブックレビュー』 判例タイムズNo.1176 117ページ)
と評されており、55期(2002年10月 司法修習終了)の若手の判事補が中心になってまとめられた『フランチャイズ契約関係訴訟について』という論考(判例タイムズNo.1162 33ページ)の中でも無媒介にそのままそっくり引用されていることからして、「制定法万能主義」に立脚した「要件事実万能論」の立場に立つ法律家の間では「定説」として扱われているものと考えて間違いないようです。このことは、「非典型契約」を意識して積極的に取り上げようという方針のもとに編纂されている「講座 現代の契約法 各論2」(編集代表 内田貴、門口正人 青林書院 2019年4月7日刊 388ページ 原悦子、西向由美、中林憲一執筆)の中でも、フランチャイズ契約の法的性質について、前掲の金井先生の説明が小塚荘一郎先生の説と同格に、あるいは見ようによっては小塚説を凌駕するかのような扱いで、紹介されていることからも知ることができます。
しかし、私には、弁護士K先生のフランチャイズ契約の定義に積極的な意味を見出すことはできません。一言でいうならば、金井先生の説に接しても、ほんの少しもフランチャイズ契約に対する理解が深まらないと思われるからです。弁護士K先生の説については、決定的な短所を、もっと具体的に、形式面と内容面についてそれぞれ一つずつ上げることができます。
形式面の決定的な短所は、弁護士K先生の場合も「準委任」という「不得要領典型契約」が縦横無尽に使用されていることにあります。金井先生のフランチャイズ契約の説明の中では、フランチャイザーが委任者の「準委任」とフランチャイジーが委任者の「準委任」が、両者の関係について何の説明もなしに並列して語られています。後半でなされている要約の中では、フランチャイザーとフランチャイジーというフランチャイズ契約の対立する二当事者の権利・義務のベクトルが正反対の方角を向いている二つの「準委任」が、同一の構成要素として区別もされていません。これでは、フランチャイズ契約の内容や構造の理解は少しも深まりようがありません。こんな無謀な芸当ができるのは、一にも二にも「準委任」という典型契約が無色透明で、しかも、無味無臭だからであり、一言で言ってしまえば、無内容だからです。
内容面の決定的な短所は、フランチャイズ契約にとって最も重要な「フランチャイジーの営むビジネス」とそこから得られた利益に連動する「ロイヤルティ」への言及がどこにも見当たらないことです。この沈黙には理由があります。というのも、フランチャイズ契約の場合、金井説の①と②と③は一体のものなのであり、区分して論じること自体が誤っているからです。この①と②と③は、「フランチャイズ・パッケージ」の構成要素です。そして、この「フランチャイズ・パッケージ」のフランチャイジーによる商業的な利用が「フランチャイジーの営むビジネス」であり、また、「フランチャイズ・パッケージ」のフランチャイザーによる利用許諾の「対価」としてフランチャイジーからフランチャイザーに支払われるのが、「ロイヤルティ」に他ならないのです。一見すると、①と②はフランチャイザーが権利者なのに、③はフランチャイザーが義務者のように見えるかもしれませんが、③は「フランチャイズ・パッケージ」の継続的な利用に不可欠な、フランチャイザーによる「フランチャイズ・パッケージ」についてのアフターサービスやメインテナンスやバージョンアップなどなのであり、「フランチャイズ・パッケージ」の他の要素と切り離すことのできない、不可分な一部なのです。弁護士K先生の説は、「フランチャイズ・パッケージ」の持つこのような不可分一体性がその視野から全く外れており、だからこそ、「フランチャイズ・パッケージ」の持つこのような不可分一体性が全く見えない構造になっており、「フランチャイズ・パッケージ」のバラバラにされた要素は、「準委任」を二個使うなどして無秩序に並列されているので、「フランチャイジーの営むビジネス」や「ロイヤルティ」が入り込む隙間がなくなってしまったのです。
フランチャイズ契約は、正しくは、どのようなものとして説明されるべきものなのかについて、最後に少しだけ、言及します。それは、小塚先生のビジネス・フォーマット型フランチャイズにおけるフランチャイズ契約の定義(小塚荘一郎 『フランチャイズ契約論』 有斐閣 2006年8月30日刊 45ページ)で、以下のようなものです。
「フランチャイザーがフランチャイジーに対して、「ファランチャイズ・パッケージ」の利用を認めるとともにその使用を義務づけること
フランチャイジーは「フランチャイズ・パッケージ」の利用に対して対価を支払う義務を負うこと
(フランチャイジーによる顧客との:筆者加筆)商品・サービスの取引を目的とした契約であること
フランチャイジーは自己の名義および計算においてこの取引を 行なうものであること
「フランチャイズ・パッケージ」の内容として、
⒜ 共通の標識および統一的な外観の使用
⒝ フランチャイザーからフランチャイジーに対するノウ
ハウの付与
⒞ フランチャイザーによるフランチャイジーの経営の継
続的な支援が規定されていること」
これこそがビジネス・フォーマット型フランチャイズ契約の正しい定義というか説明です。私は、この中のどこにも「典型契約の用語の切れ端」など見当たらないことに、よくよく注意をしなければいけないと思います。
変化を直視できない要件事実

購入したての時は、売主によって直前に行われたリフォームのせいで新築のようにきれいな部屋だったのに、入居して日もたたないうちに、カビがどんどんひどくなり、ついには天井の一部が劣化で崩落してしまった、というマンションの一室の買主から相談を受け、購入契約の詐欺による取り消しの訴訟に踏み切ったことがあります。その訴訟では、争点整理の手続の席上で、詐欺の要件である欺罔行為について、裁判官から「本件の欺罔行為は『その部屋の不具合の隠蔽』だという主張のようだが、隠蔽しようとした不具合とは「購入契約のころにその部屋に生えていたカビの存在、と理解してよいか。」という釈明がありました。私は、「そのような要約では十分だとは言えない。『その時そこに生えていたカビ』そのものではなく、『徐々にその範囲を広く深くし、ついには天井や壁の部材を劣化させ、天井の一部崩落までをも招来してしまったようなカビの存在』こそが、この部屋の売主が隠蔽しようとしたこの部屋の不具合である。売主がリフォームで隠蔽しようとしたこの部屋の不具合というのは、そのときついていた壁の汚れやシミの醜い外見と同じような意味で、そのとき生えていた『カビ』の醜い外見というような表面的なものではない。」と反論しました。ところが、この反論は、裁判官には、まるで理解してもらえませんでした。裁判官からは、かえって、「今行っているのは、欺罔行為という要件事実を本件に当てはめるために必要な事実関係の整理なのであって、端的に言えば、欺罔行為の対象の主要事実は何かということだ。間接事実や事情については主張してもらう機会を別に設けるから、この場では、主要事実に議論を集中してもらいたい。」とたしなめられてしまいました。しかし私は納得できたわけではなかったので、「カビ、といっても、もっとダイナミックに理解しないといけない。カビは時間軸の中で変化していくものなのだし、変化にも、広がりや深さ、そして速度などにさまざまな種類のものがある。裁判官が言うようにスタティックにカビをとらえても、本件の欺罔行為の全体像は理解できない。それ以上広がる可能性のない壁のシミなら、その存在を隠したところで欺罔行為という詐欺の中心的な要件に達するほどのレベルのダマシになどならない。増殖の結果今ここにあり、これから先も異常なテンポで広がっていくことが容易に予想できるようなカビを隠蔽しようとしたからこそ、その隠蔽が持つ行為の性格が、「欺罔行為」と評価されてしかるべき深刻なレベルのものとなったのだ。」と一応は食い下がってみました。しかしながら、それ以上反論してもくどくなるだけだという思いもあったので、その場での発言は、そこまでで差し控えました。
これに類した経験、つまり、裁判官が、ことさら、のっぺりとした、平板で、潤いに欠ける言葉を好み、結果として事案の持つ「個性」への肉迫の障碍となってしまっているのではと思われるような場面には、何度も遭遇したことがあります。しかも、短絡的にそのまま結論まで出そうとするので、頭を抱えたことも何度もありました。そんなとき私が裁判官に対して、実際はそこまでのことはしないのですが、思わず口に出してしまいたくなるのが、「物事というのは、時間軸の中で変貌をとげていくものなのだから、『今どうか』ということも大切だが、『今のこの状態は変化していくかもしれない』、『どう変化していくのだろう』ということも念頭に置いた柔軟な見方をしていかなければ理解できないものなのではないか。」という不満の言葉です。とは言うものの、こうした事態に「動的に(ダイナミックに)」、「静的に(スタティックに)」という言い方をくり返してばかりいるうちに、なんとなく底が浅いというか、「ちょっと違うんじゃないかな。」というような気がするようになってきました。「どういう言葉が、この場合適切なのだろう。」などと考えていたとき、ふと頭に浮かんできたのが若いころ聞きかじったことのある「潜勢態」という言葉でした。そして、この「潜勢態」というアリストテレスの哲学で使われている用語にたどり着いて、私はようやく、直面している事態の全体像が見えてきたように思えてきたのです。
「潜勢態」というのは、アリストテレスの哲学のもっとも本質的な概念の一つである「運動変化」の重要な下位概念の一つです。テキストの性格から、引用が困難なので、やむを得ず、私に理解できる範囲で、という制約のもとにではありますが、説明を試みてみることにします。
「もの」の本質は「運動変化(キーネ-シス)」にあります。その運動変化というプロセスの両極端に「別の在り方への可能性をいまだ発現させていない『可能態(デュナミス、【潜勢態】と訳されることもある言葉です)』」という状態と、「そのものの在り方を発現しきった『終極実現態(エネルゲイア【よく似た概念としてエンテレケイアという哲学用語が区別して使われることもあります】)』」という状態があります。存在しているものの中に秘められている「可能態」の一部が「運動変化」して存在しているものの中で「終極実現態」という状態となり、そのものを構成する部分となります。もっとも、存在しているものの中にあるすべての「可能態」が「運動変化」してしまい、存在しているものが「終極実現態」だけからなるものになり、その存在の中から「可能態」がなくなってしまうということは人間社会の中ではありえません。変化して「終極実現態」になるのは、存在しているあるものの中にあった「可能態」の一部でしかありませんから、存在しているものは、「終極実現態」としての側面と「可能態」としての側面をいつも同時に有するし、だからこそ、次の瞬間にも、また、変化が生じるかもしれないとされているのです。(アリストテレス : 『新アリストテレス全集 4 自然学』 内山勝利訳 岩波書店 2017年11月22日刊 第三巻 第一章 116ページ ; 『旧アリストテレス全集 12 形而上学』 出 隆訳 岩波書店 1968年4月27日刊 第五巻 第十二章 161ページ、 同 第九巻 第一章 289ページ、 同 第十一巻 第九章 383ページ)。
稚拙な要約ですが、こうしたアリストテレスの考え方は、まさに、存在するものの本質をつくものであるように私には感じられます。
冒頭に書かせていただいた、裁判官の発想に対する違和感は、たぶん裁判官のものに対する見方の中に、「そのものに内在しているデュナミス的側面とエネルゲイア的側面を適切に両睨みしていかなければそのものを本当に分かったことにはならない」という問題意識についての感覚が欠如し、エネルゲイア的側面(既にそのものに形として表れているもの)しか見ようとしないことが大きいのではないかと思っています。問題になった「不具合」に戻るとするなら、「今はカビどころか何の汚れもない真っ白な壁の中にも、明日カビが生えてくる部分がある」という状態のことを「不具合」というのです。
こうしたことが、裁判所という、本来もっとも知的で洗練された空間であるはずのところで、大量現象として「デュナミス(潜勢態)」の無視という事態が展開しているのは、考えてみれば不思議なことです。原因を考えてみたこともありました。当たっているかどうかも不確かですし、上手く説明ができるわけではないのですが、感覚的には「要件事実」をすべてに優先して重視しようという、このところの裁判所の姿勢にその責任の大きな一端があるように思います。その中でも、とりわけ直接に関係がありそうなのは、「要件事実論」の中で強調されている「過剰主張の禁止(不寛容)」あるいは「ミニマムの原則」と呼ばれる考え方なのかもしれません。「過剰主張の禁止」は、要件事実だけでなく、間接事実や事情にも及ぶという「考え方」に接して、私は、自分が一生懸命に作成した、自分としては出来が良いと思われた(事件とその周辺の状況をパースペクティブとしてまとめて呈示できた気がしたということです。)準備書面が時として裁判官に煙たがられてしまうのはなぜなのか、その理由の一端が、分かったような気がしました。
しかしこの問題の実相は、もう少し根深いような気もします。というのも、目の前にある「事実」を純粋な「要件事実」に近づけようとすればするほど、多分、「事実」は「静止した記号でしかないもの」に近づいてしまうということなのではないかと思われるからです。これも法的安定性には役に立ちそうな「もの」についての見方の一つには違いないのかもしれませんが、それだけでは一面的に過ぎるでしょう。一面的な見方が強調される中にあっても、常に多面的にものを見ていくことについての意識を忘れないようにしていかないと、法律実務家のものの見方は退化してしまうのではないか、やや大げさですが、そんな危惧の念が、私の頭をよぎりました。
強くなってきたこだわり

当職には、年を追う毎に、高名な論攷の掉尾を飾る一節に対するこだわりの気持ちが強くなってきました。それは、以下のとおりのものです。
「こうした文化発展の最後に現れる『末人たち(die letzte Menschen)』にとっては、次の言葉が真理となるのではなかろうか。『精神のない専門人、心情のない享楽人。この無のもの(dies Nichts)は、人間性のかつて達したことのない段階にまですでに登りつめた、と自惚れるだろう』。」
(マックス・ヴェーバー著 大塚久雄訳「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」ワイド版岩波文庫 366ページ)
極めて抽象的な「予言」ですが、現在の社会全体を見渡した場合、市場原理主義を信奉する人々やファンド資本主義につかりきった人々を筆頭にして、この一節は、確かに今を生きる多くの人々にあてはまるかもしれないもののように思われます。「末人たち」については、基本的には、資本主義社会の中で経済的に成功した「勝者」と呼ばれることもある大金持ちのことを本来意味するものなのでしょうが、スマートフォンでSNSに熱中している若者が無関係かと問われれば、そうでもないような気もします。しかし、この論攷がはじめて世に出たのは1905年のことでした。当時のウェーバーが、市場原理主義やファンド資本主義を、あるいはスマートフォンのことを具体的に知っていたはずはありません。では、ウェーバーは、具体的にどんな人物像を念頭において、この一節を書いたのか、このことが、私にとって、昔から気になる謎でした。というのも、このことが分ると、「無自覚に毎日を過ごしていると、はまってしまうかもしれないこの罠から抜け出すためには、どうすればよいのか。」という問いに、答えが出せるかもしれないと考えたからです。
弁護士は、あるいはもっと広く、裁判官や検察官も加えた法曹は、こんな「末人」になってはならない責務があるのだろうと思います。しかし、現代という時代に生きていることそれ自体からして、よほど注意していないと、何時「末人」の末席を汚すようなことになってしまうかもしれません。こういった問題意識は、年々歳々強まってきました。ですから、冒頭のこだわりは、このところ、一段と強くなってきたのです。私としては、簡単にあきらめてしまったり、気を弛めてしまったりといったことのないようにと意を用いながら、日々、仕事にいそしんでいます。