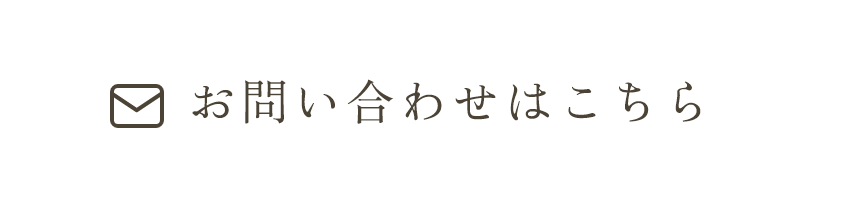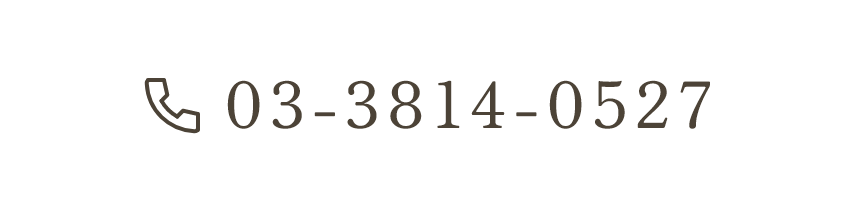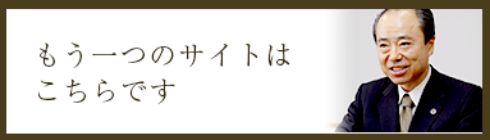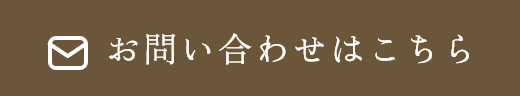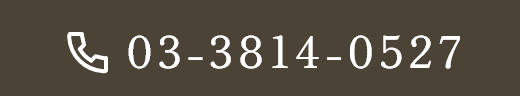法解釈学を身につけようとした経済学部生の戸惑い

私は、弁護士を始めて40年を越えました。しかし、私は、どこの大学であれ法学部に籍を置いたことはありません。私の経歴は、東大の経済学部を卒業し、大学院経済学研究課の修士課程を一応終了し、形式的に博士課程に1年間籍を置かせてもらい、中退して、そのまま司法研修所に入所し、弁護士になったというものでした。
私は、まだ東大に赴任して2年目の肥前榮一先生のゼミに所属し、西洋経済史とりわけ大塚史学の教えをうけ、マックス・ウェーバーのことも教えてもらいました。私は、マックス・ウェーバーの理論的な枠組みをもっと知りたいと思い、研究者になればよいのだろう、というやや安易な気持ちで大学院に入りました。ここまでは、とりたてて、これといった特色もない人生の歩みだったのですが、ある時、魔がさしたというか、ふと、何か別のことをしてみようという気になりました。その時、中途半端に、司法試験というものがあるということを知ったのが、ある意味、運の尽きで、それまで、全く未知の分野だった法律の試験勉強の道に足を踏み入れることになったのです。
私は、試験に受かるために、法解釈学を一から学んでいく必要に迫られたのですが、冒頭から、一番目の、それほど深刻ではない、しかし、後になって振り返ってみると失笑ものの失敗をしました。私は、まず、「何かきちんとした書籍を読めば良いのではないか。」と考えました。というのも、受験生から「教科書」などと呼ばれていた民法や商法の「解説書」は、当時の私には、何となく、安っぽい感じがしたからです。そこで私は、現在も名著として定評があると思いますが、当時法律学の専門書としてとても有名だった、我妻榮先生の「近代法における債権の優越的地位」や川島武宣先生の「所有権法の理論」を読むことにし、実際、読むことは読みました。しかし、この読書は、言ってしまえば、時間の無駄でしかなく、試験勉強とは、全く無縁のものでしかありませんでした。無縁であるというより、通読というか読破したとはいうものの、当時の私にとっては、分かるところが分かったにすぎないことを思い知らされただけだったのです。せっかく、苦労して、難しい本を読んだのに、読書の前と後で、自分の法律というものについての内在的な理解に何の変化も生じませんでした。こうした事態に直面して、ようやく私にも「そうか、アカデミックな気分は邪魔なだけなんだ。」「私が、行なおうとしているのは試験勉強なのだから、アカデミックな気分は、完全に捨ててかからなければだめなんだ。」という当たり前のことが、腹におちて分かりました。そして、この反省を足掛かりにして、もっと、法解釈学という技術を身につけるような努力をしようと決意を新たにすることができたのです。
こうして、私は、少し遠回りはしましたが、ようやく、「基本書」と呼ばれている、民法なら民法、刑法なら刑法といったそれぞれの法律の体系書を座右に置いて、勉学にいそしむという司法試験の王道にたどりつくことができました。この「基本書」こそ、少し前に、不遜にもアカデミックな専門書と比べて「安っぽい感じがした」などと評した「解説書」でした。しかし、実際に手にして読み進んでいくと、「安っぽい」などと評せるようなしろものでなどないことが、よく分かりました。賢人の手による学問の薫りの高い書籍、それが「基本書」に対して下されるべき正しい評価でした。私は、ようやく、何冊もの「基本書」に取り囲まれ、何冊もの「基本書」の中に飛び込んでいく、といった、試験勉強の外的環境を手に入れることができたのです。
ところが、「これでめでたしめでたしだったか、というと、実は、そうではありませんでした。今度は、一番目の失敗より、もっともっと深刻な問題に、突き当たってしまったからです。
新たに、直面することになってしまった問題というのを、四宮和夫先生の法律学講座双書民法総則(現在は共同著作者として能見善久先生が加わり第8版となっていますので、以下では、こちらの新しい版でページなどに言及します。)を使って、具体的に説明させてもらうと、このようになります。例えば「第4章 私権の変動」の中に「第5節 代理」というひとまとまりの論稿があります。この「第5節 代理」というのは、293ページから340ページまで48ページにわたって論述がなされているのですが、私は、その内293ページから298ページまでのわずか5.5ページに書かれた「第1款 代理の意義と存在理由」は、全部ではないにせよ、おおむね、興味を持って読めました。しかし、298ページから340ページまで42.5ページにかけて続く「第2款 代理権(本人と代理人の関係)」、「第3款 代理行為」、「第4款 無権代理」、「第5款 表見代理」には、全く興味が持てませんでした。その頃、私は、司法試験の予備校にも通い、司法試験の試験勉強をしている仲間を何人も知っていたのですが、様子を見て驚きました。彼らは、「第5節 代理」を読む時に、「第1款 代理の意義と存在理由」には、ほとんど関心をみせず、飛ばし読みして、第2款以降が「世界の全てだ」という雰囲気で、四宮先生の教科書を読み進んでいっているようなのです。第2款以降が法解釈学にとって「本文」だから、そういう読み方を、能率的な読み方だと考えていたのだと、後に知りました。
「何なのだろう。今自分が目の前にし、体験させられているのは。多分自分の方が考え方を変えていかなければならないのだろうが、どこに問題があるのか分からない。どこに問題があるのか分からなければ、本当の意味で自分を変えることはできないだろう。これは大変なことになった。」と、当時、私なりに悩みました。そんな日々を送る中で、ある日、得心がいった答が、ひらめいてきました。それは、次のような仮説でした。
① 経済学を学んだものは、社会全体の本流を捉えることこそが大切なことだと考え、そうした本流をモデル化して説明しようとする。この場合、モデルに合致しないものは、例外として切捨て、その存在には関心を持たない。
② 法律学を学んだものは、社会に大量現象として生起している、言ってみれば、健全な部分には関心を持たず、関心は、もっぱら、健全な部分から逸脱した、いわば例外に集中する。そして、その関心の対象については、黒に属するのか白に属するのかが区別できて、はじめて「それ」が分かったことになる。
③ すると、①と②は、関心の対象が、真逆の関係にあることになる。
④ 経済学部で育った自分としては、①の感性を持つ人間として 育て上げられたが、司法試験の試験勉強に集中するためには、さっさと①の感性を捨て、脳をいったん白紙にして、②の発想に自らの脳を塗り替えなければならない。
今、仮に、前記の①と②を対立させることによって、私に生じた事態を説明しようとする仮説を原則例外逆転仮説と呼ばせていただくとして、四宮先生の「民法総則」に生じた現象は、この原則例外逆転仮説の立場からすれば、「第1款 代理の意義と存在理由」が、「代理」の本流の論述で、①と親和性が強く、「第4款 無権代理」などが、②と親和性の強い、「代理」の例外的事象、病理的事象をどう整序するかについての論述だという説明になります。まだ、頭が①だった私には、第1款は興味が湧き、またある程度理解ができても、②そのもののような第4款などの第2款以降には興味を持つこと自体が困難なことだったということになります。このような症状の原因について、原則例外逆転仮説は、私にとって納得感のある説明となり、当時の私の違和感も、私にとってとっては、解消することができたわけです。
この原則例外逆転仮説を他の方々にご理解いただくのは、もともと①の感性をお持ちの方に対しても、もともと②の感性をお持ちの方に対しても、容易なことではないかもしれません。そこで、私は、この仮説を説明しなければならなくなってしまった時、川の断面のイメージを、比喩として、使わせてもらったことがあります。それは、このようなものです。
原則例外逆転仮説では、岸や川底との摩擦もほとんどなく、大量の水が凄いスピードで流れている川の中心的な部分のあたりの水の流れの流速や流量などの観察や分析あるいは制御が経済学の対象ということになります。これに対して、水のよどんだ岸辺のあたりに着目し、どこまでが川で、どこからが岸かといったことに興味を集中する、あるいは、川底の苔に注目し、苔は川に属するのか、川底という陸地の末端に属するものなのかといったことについて興味をもって論じる、というのが、法律学的な関心ということになります。中州があれば、それは陸地なのか、川の中に生じた特異な現象なのか、法律学では、おおいに議論されることでしょう。
原則例外逆転仮説にたどり着いてから後、私に、経済学部出身者であるが故に背負わされるハンディは無くなりました。幸いなことに、それから程なく、試験にも合格しました。そして、現在があることを考えると、この原則例外逆転仮説の啓示は、この仮説が客観的に正しいものなのか否かという問題より、私の人生の、転機の象徴そのものだったと、今でもつくづく考えています。
(初出『経友』№185/2013年2月号)
GHQの経済政策と制度学派経済学

現在の日米関係は、明らかに対等なものとは言えないものですが、このいびつな関係は、占領下のそれとは大きく異なるものであることも事実です。占領下の日米関係というと、ともすれば、「支配従属関係」といった、屈辱的なものを連想し勝ちかもしれません。そういった側面があったことを否定するつもりはありませんが、こと、経済政策に限ってみれば、占領下の日米関係、言い方を変えれば、占領軍が日本社会に及ぼした影響の中に、積極的な、あるいは、肯定的なものが見て取れることを無視すべきではありません。しかも、そうした政策の実施主体は、体系的な考え方のもとにまとまっていました。
このような、積極的、あるいは、肯定的な政策の実施主体は「制度学派経済学」に依拠していた「ニューディーラー」と呼ばれるグループでした。当時GHQの一員として「財閥解体」を担当していたエレノア・M・ハドレーは、当時を回想した著書(エレノア・M・ハドレー + パトリシア・ヘーガン・クワヤマ 共著 財閥解体 GHQエコノミストの回想)の中で、「占領について自分の経験を書いたセオドア・コーエン(コロンビア大学大学院で学んだ制度学派経済学派に属する労働経済学者)は、研究に『日本の再構築:占領期のニュー・ディールとしての役割』という題をつけた。占領はまさにニュー・ディールであった。占領政策は確かにニュー・ディール構想に沿った部分がたくさんあった。」と論じています(ハドレー外 前掲書 111ページ)。そもそも、GHQ内で民主的改革推進の中心人物だった、「民政局」次長のC・L・ケーディスも「ニューディーラー」でした(竹前栄治 著 GHQ 107ページ)。
日本の経済学の学会では、「制度学派経済学」あるいはこれを包含する「制度派経済学」は、その本流からは、ほぼ完ぺきに無視されているので、権威のある研究者による体系的な研究などに接することは期待できないでしょう。しかしながら、「制度学派経済学」に裏付けられた「ニューディーラー」が、GHQの活動の一環として、あるいは、「制度学派経済学」の活動の一環として、当時の日本にもたらした施策は、現在の日本社会をどう見るかという観点からしても、あるいはもっと広がりのある観点からしても、見落とすことのできない多くの教訓を内包したものだと思われるのです。
GHQの経済政策は、多岐にわたりますが、ここでは、「財閥解体」、「労働改革」、「農地改革」、「シャウプ税制導入」に着目してみることにします。「財閥解体」は、「ハドレー外 前掲書」の著者であるエレノア・M・ハドレーなどによって遂行されました。しかし、ハドレーは、1950年から1966年までレッド・パージの対象とされたことも知られています(ハドレー外 前掲書 33ページ。)。ここでは、やや単純化して議論を進めていますが、GHQの権力構造は一筋縄ではいかないものであったようです。「労働改革」は、「制度学派経済学」派に属するセオドア・コーエンなどによって遂行されました。「農地改革」は、もともと日本のエリート官僚によって計画されていたものだったのですが、当時、日本の国会に「農地改革」の法案が上程されたところ、在村地主の権益の擁護(小作人に売らなくてもよい農地の面積の大幅な拡大)という骨抜きをされそうになったということがありました(このエピソードの存在を、私は重視しています。というのも占領政策に否定的だった当時の論者は、所詮、戦前の支配階級の傀儡に過ぎないことを、分かりやすい形で示しているからです。)。このことを知ったGHQが「農地改革についての覚書」という「指令」を発出したことによって骨抜きは阻止されました(大和田啓氣 秘史 日本の農地改革 | 農政担当者の回想 79ページ以下)。こうしたいきさつから、農地改革もまた、ニューディーラーの関与によって、はじめて実現させることが出来たものだったと考えて良いでしょう。
GHQの経済政策を語る上では、「シャウプ税制導入」も避けて通ることは出来ません。とはいうものの、「シャウプ税制導入」と制度学派経済学との関係は、やや難問です。そもそも、税制使節団長のカール・S・シャウプは、コロンビア大学、商学部教授兼政治学部大学院教授で、狭義の経済学者ではありませんでした。しかし、制度学派経済学は、隣接する学問との関係が強かったこと(制度学派経済学を代表するといわれているソースティン・ヴェブレンは、社会学を兼任する学者でした。)、制度学派経済学の拠点となっていたのがコロンビア大学であったところ、シャウプはコロンビア大学の教授であり、7名からなる税制使節団の委員の内、3名がコロンビア大学の教授であっったこと(山下壽文 著 戦後税制改革とシャウプ勧告 3ページ)などから、シャウプ税制導入もまた(ニューディーラーが挙行したものだ、とまで断言することはできないかもしれませんが、)制度学派経済学の影響のもとに実施されたものだったということは間違えないと思われます(金子宏 著 租税法理論の形成と解明 上巻 224ページ)。
このように、GHQによって行われた経済政策は、制度学派経済学を背景としてニューディーラーたちの手によって、体系的に行われたものでした。制度学派経済学に導かれたGHQの経済政策が、その後、日本の資本主義経済が発展していくために必要な「初期条件」を整備してくれたことは、議論の余地はないと思われます。戦後の日本の「高度経済成長」は、GHQの経済政策の賜物だったということになるのです。制度学派経済学にとっても、多分、GHQの経済政策への関与は、自分たちの理論の正しさを実証することを目的とした大掛かりな社会実験だったのだと思われます。
制度学派経済学は、現在も、GHQを通して日本で行ったような活動を続けているようです。このことを教えてくれたのは、東大で教授をしていた友人でした。友人は、 (Douglass C. North , John Joseph Wallis , Steven B. Webb and Barry R. Weingast Limited Access Orders : Rethinking the Problems of Development and Violence) といった小論(英語のWebにアップされています。)を紹介してくれました。紹介された小論は、国民経済を「リミテッド・アクセス・オーダー」の国と「オープン・アクセス・オーダー」の国に類型化し、発展途上国に対して、これまで、その経済発展を「リミテッド・アクセス・オーダー」のモデルで解決しようとしがちだったと総括しました。そのうえで、これからは、発展途上国に対し、その経済発展を「オープン・アクセス・オーダー」のモデルに依拠してすべきだという提言が、この小論のポイントでした。
「リミテッド・アクセス・オーダー」というのは、「一部の者にしかチャンスが与えられていない体制」とでも訳せる学術用語です。伝統的には、「開発独裁」と呼ばれるもので、権威主義的な政治権力と財閥が手を組んで開発途上国である自国の経済をけん引していくという手法です。ここでは、一般の国民は、政治活動の中心にも経済活動の中心にも関与することができません。これに対して、「オープン・アクセス・オーダー」というのは、「チャンスが全員に開かれている体制」と訳せる学術用語です。ここでは、政治活動にも経済活動にも、全員が参加できます。これまで、こうしたチャンスが全員に開かれている社会は、先進国でしか実現できないと考えられてきました。しかし小論の中で、ダグラス・ノースたちは、発展途上国を指導していく姿勢の問題として、「『リミテッド・アクセス・オーダー』は行き詰まっており、『オープン・アクセス・オーダー』への移行が模索されるようになってきている。これからは、『オープン・アクセス・オーダー』を発展途上国の経済発展のモデルとして採用していくべきだ。」と論じているのです。
このLimited Access Ordersという小論は、GHQの経済政策における制度学派経済学の問題関心、あるいは、「GHQによる占領」の前と後の日本の社会の変容についての理解の仕方という観点からして、極めて示唆に富むものであると思います。というのも、明治維新以来の日本の経済発展を俯瞰してみると、日本の経済の「アクセス・オーダー」は、第2次世界大戦の前後で全く異なったものに変質していることを見て取ることができるからです。明治維新から第2次世界大戦前まで、日本は、典型的な「リミテッド・アクセス・オーダー」の国でした。しかも、経済発展という面では、それなりに成功していました。ここに、突如として「GHQによる占領」という断絶が介在します。「GHQによる占領」の中で、制度学派経済学に依拠した「ニューディーラー」がGHQの経済政策を通して実現したかったのは、日本の「オープン・アクセス・オーダー」への方向転換でした。「GHQによる占領」の後、「オープン・アクセス・オーダー」の国として、日本の経済は発展することができたという訳です。
しかし、制度学派経済学に導かれたGHQの経済政策が日本に及ぼしたプラスの影響にも限界があったようでした。戦後の日本の「高度経済成長」は、バブル崩壊後、息切れしてしまったからです。息切れは、現在も解消できていません。このことは、多分、制度学派経済学に導かれたGHQの経済政策が日本に植え付けてくれた、日本の資本主義経済が発展していくために必要な「初期条件」が、時間の経過とともに劣化し、通用しなくなってしまったことと無関係ではないでしょう。日本は、制度学派経済学に導かれたGHQの経済政策がもたらしてくれた「初期条件」のもとで40年以上繁栄を謳歌してきたのですから、「アクセス・オーダー」をバージョン・アップし、次の発展に向けた新たな経済インフラのフレ-ムづくりに専念しなければならなかったはずだったのではないでしょうか。しかし、現実の日本では、今日に至るも、そうした動きは何も見られませんでした。
さらに言うとすれば、スタート・アップ企業への待遇も問題かもしれません。GHQの経済政策は、単に日本経済一般を底上げしただけでなく、日本を、世界に通用するスタート・アップ企業の揺籃場にしました。事実、このころ、ソニーやホンダなどが創業して、後に、世界規模で、大きな成功を収めています。スタート・アップ企業の重要性は、最近の日本でも意識されるようになり、その育成に力を入れようとしているようです。しかしながら、今のところ、そうした取り組みから産声を上げたスタート・アップ企業は、どれも小ぶりで、国際性に乏しく、既存の技術の思い付き的応用にとどまっているように思えてなりません。GHQの経済政策がもたらしたスタート・アップ企業と現代のスタート・アップ企業の違いは、おそらく、GHQの経済政策がスタート・アップ企業にとっても望ましい「初期条件」をもたらしたのに対して、現代のスタート・アップ企業にはそうした「初期条件」が用意されていないことによるものと思われます。こうしたことも含めて、現在の日本は、あらゆる面で、経済インフラのフレームの整備を迫られているということができると思われるのです。
私は、弁護士を始めて40年を越えました。しかし、私は、どこの大学であれ法学部に籍を置いたことはありません。私の経歴は、東大の経済学部を卒業し、大学院経済学研究課の修士課程を一応終了し、形式的に博士課程に1年間籍を置かせてもらい、中退して、そのまま司法研修所に入所し、弁護士になったというものでした。
私は、まだ東大に赴任して2年目の肥前榮一先生のゼミに所属し、西洋経済史とりわけ大塚史学の教えをうけ、マックス・ウェーバーのことも教えてもらいました。私は、マックス・ウェーバーの理論的な枠組みをもっと知りたいと思い、研究者になればよいのだろう、というやや安易な気持ちで大学院に入りました。ここまでは、とりたてて、これといった特色もない人生の歩みだったのですが、ある時、魔がさしたというか、ふと、何か別のことをしてみようという気になりました。その時、中途半端に、司法試験というものがあるということを知ったのが、ある意味、運の尽きで、それまで、全く未知の分野だった法律の試験勉強の道に足を踏み入れることになったのです。
私は、試験に受かるために、法解釈学を一から学んでいく必要に迫られたのですが、冒頭から、一番目の、それほど深刻ではない、しかし、後になって振り返ってみると失笑ものの失敗をしました。私は、まず、「何かきちんとした書籍を読めば良いのではないか。」と考えました。というのも、受験生から「教科書」などと呼ばれていた民法や商法の「解説書」は、当時の私には、何となく、安っぽい感じがしたからです。そこで私は、現在も名著として定評があると思いますが、当時法律学の専門書としてとても有名だった、我妻榮先生の「近代法における債権の優越的地位」や川島武宣先生の「所有権法の理論」を読むことにし、実際、読むことは読みました。しかし、この読書は、言ってしまえば、時間の無駄でしかなく、試験勉強とは、全く無縁のものでしかありませんでした。無縁であるというより、通読というか読破したとはいうものの、当時の私にとっては、分かるところが分かったにすぎないことを思い知らされただけだったのです。せっかく、苦労して、難しい本を読んだのに、読書の前と後で、自分の法律というものについての内在的な理解に何の変化も生じませんでした。こうした事態に直面して、ようやく私にも「そうか、アカデミックな気分は邪魔なだけなんだ。」「私が、行なおうとしているのは試験勉強なのだから、アカデミックな気分は、完全に捨ててかからなければだめなんだ。」という当たり前のことが、腹におちて分かりました。そして、この反省を足掛かりにして、もっと、法解釈学という技術を身につけるような努力をしようと決意を新たにすることができたのです。
こうして、私は、少し遠回りはしましたが、ようやく、「基本書」と呼ばれている、民法なら民法、刑法なら刑法といったそれぞれの法律の体系書を座右に置いて、勉学にいそしむという司法試験の王道にたどりつくことができました。この「基本書」こそ、少し前に、不遜にもアカデミックな専門書と比べて「安っぽい感じがした」などと評した「解説書」でした。しかし、実際に手にして読み進んでいくと、「安っぽい」などと評せるようなしろものでなどないことが、よく分かりました。賢人の手による学問の薫りの高い書籍、それが「基本書」に対して下されるべき正しい評価でした。私は、ようやく、何冊もの「基本書」に取り囲まれ、何冊もの「基本書」の中に飛び込んでいく、といった、試験勉強の外的環境を手に入れることができたのです。
ところが、「これでめでたしめでたしだったか、というと、実は、そうではありませんでした。今度は、一番目の失敗より、もっともっと深刻な問題に、突き当たってしまったからです。
新たに、直面することになってしまった問題というのを、四宮和夫先生の法律学講座双書民法総則(現在は共同著作者として能見善久先生が加わり第8版となっていますので、以下では、こちらの新しい版でページなどに言及します。)を使って、具体的に説明させてもらうと、このようになります。例えば「第4章 私権の変動」の中に「第5節 代理」というひとまとまりの論稿があります。この「第5節 代理」というのは、293ページから340ページまで48ページにわたって論述がなされているのですが、私は、その内293ページから298ページまでのわずか5.5ページに書かれた「第1款 代理の意義と存在理由」は、全部ではないにせよ、おおむね、興味を持って読めました。しかし、298ページから340ページまで42.5ページにかけて続く「第2款 代理権(本人と代理人の関係)」、「第3款 代理行為」、「第4款 無権代理」、「第5款 表見代理」には、全く興味が持てませんでした。その頃、私は、司法試験の予備校にも通い、司法試験の試験勉強をしている仲間を何人も知っていたのですが、様子を見て驚きました。彼らは、「第5節 代理」を読む時に、「第1款 代理の意義と存在理由」には、ほとんど関心をみせず、飛ばし読みして、第2款以降が「世界の全てだ」という雰囲気で、四宮先生の教科書を読み進んでいっているようなのです。第2款以降が法解釈学にとって「本文」だから、そういう読み方を、能率的な読み方だと考えていたのだと、後に知りました。
「何なのだろう。今自分が目の前にし、体験させられているのは。多分自分の方が考え方を変えていかなければならないのだろうが、どこに問題があるのか分からない。どこに問題があるのか分からなければ、本当の意味で自分を変えることはできないだろう。これは大変なことになった。」と、当時、私なりに悩みました。そんな日々を送る中で、ある日、得心がいった答が、ひらめいてきました。それは、次のような仮説でした。
① 経済学を学んだものは、社会全体の本流を捉えることこそが大切なことだと考え、そうした本流をモデル化して説明しようとする。この場合、モデルに合致しないものは、例外として切捨て、その存在には関心を持たない。
② 法律学を学んだものは、社会に大量現象として生起している、言ってみれば、健全な部分には関心を持たず、関心は、もっぱら、健全な部分から逸脱した、いわば例外に集中する。そして、その関心の対象については、黒に属するのか白に属するのかが区別できて、はじめて「それ」が分かったことになる。
③ すると、①と②は、関心の対象が、真逆の関係にあることになる。
④ 経済学部で育った自分としては、①の感性を持つ人間として 育て上げられたが、司法試験の試験勉強に集中するためには、さっさと①の感性を捨て、脳をいったん白紙にして、②の発想に自らの脳を塗り替えなければならない。
今、仮に、前記の①と②を対立させることによって、私に生じた事態を説明しようとする仮説を原則例外逆転仮説と呼ばせていただくとして、四宮先生の「民法総則」に生じた現象は、この原則例外逆転仮説の立場からすれば、「第1款 代理の意義と存在理由」が、「代理」の本流の論述で、①と親和性が強く、「第4款 無権代理」などが、②と親和性の強い、「代理」の例外的事象、病理的事象をどう整序するかについての論述だという説明になります。まだ、頭が①だった私には、第1款は興味が湧き、またある程度理解ができても、②そのもののような第4款などの第2款以降には興味を持つこと自体が困難なことだったということになります。このような症状の原因について、原則例外逆転仮説は、私にとって納得感のある説明となり、当時の私の違和感も、私にとってとっては、解消することができたわけです。
この原則例外逆転仮説を他の方々にご理解いただくのは、もともと①の感性をお持ちの方に対しても、もともと②の感性をお持ちの方に対しても、容易なことではないかもしれません。そこで、私は、この仮説を説明しなければならなくなってしまった時、川の断面のイメージを、比喩として、使わせてもらったことがあります。それは、このようなものです。
原則例外逆転仮説では、岸や川底との摩擦もほとんどなく、大量の水が凄いスピードで流れている川の中心的な部分のあたりの水の流れの流速や流量などの観察や分析あるいは制御が経済学の対象ということになります。これに対して、水のよどんだ岸辺のあたりに着目し、どこまでが川で、どこからが岸かといったことに興味を集中する、あるいは、川底の苔に注目し、苔は川に属するのか、川底という陸地の末端に属するものなのかといったことについて興味をもって論じる、というのが、法律学的な関心ということになります。中州があれば、それは陸地なのか、川の中に生じた特異な現象なのか、法律学では、おおいに議論されることでしょう。
原則例外逆転仮説にたどり着いてから後、私に、経済学部出身者であるが故に背負わされるハンディは無くなりました。幸いなことに、それから程なく、試験にも合格しました。そして、現在があることを考えると、この原則例外逆転仮説の啓示は、この仮説が客観的に正しいものなのか否かという問題より、私の人生の、転機の象徴そのものだったと、今でもつくづく考えています。
(初出『経友』№185/2013年2月号)
「営利事業」の主体

様々な形態の営利事業
「営利事業」は、「元手としての財」にうまく働きかけて利益を得ようというの営みの総称です。そこで、「営利事業」は、「財」に対する「人間」や「人間」が作り上げた制度的枠組み(これらの総称が「『営利事業』の主体」と呼ばれるものです。)との関わり方という観点から、いろいろなかたちをとって行われてきたことが知られています。そして、現代においては、その関わりの形態は「株式会社」というものに収斂しました。ところが、この肝心かなめの「株式会社」をどのようなものとして理解すべきかについて、かなり深刻な混乱というか対立が生じています(岩井克人「会社の新しい形を求めて なぜミルトン・フリードマンは会社についてすべて間違えたのか」 一橋ビジネスレビュー 2020 WIN 8ページ)。どうして、このような「株式会社」に対する理解の混乱や対立が生じたのか、もしかしたら、「元手としての財」に対する人間の格闘の場だった「『営利事業』の主体」の全体像をあらためて俎上にのせ、検討を加えれば、何かのヒントが得られるかもしれません。こうした問題意識をもって、「『営利事業』の主体」をいくつかの類型に分けたうえで、そうした、いくつかの「『営利事業』の主体」の機能や構造、長所や弱点を論理的に整理し、相互の関連性、緊張関係を明らかにしてみたいと思います。
「『営利事業』の主体」は、いろいろなかたちをとって、人間社会に現れては消え、また現れては消え、ということを繰り返してきました。そこで、この「『営利事業』の主体」は、一見するとどこに着目して類型化したらよいかの手がかりも、容易には見つからないもののように思われます。それはそのとおりなのでしょうが、私の考えでは、「『営利事業』の主体」は、
①「1人の自然人vs複数の自然人」という二項対立
②「グループとしての(複数の)自然人vs法人」という二項対立
③「持分会社vs株式会社」という二項対立
④「初期の株式会社vs成熟株式会社」という二項対立
⑤「成熟株式会社vs爛熟株式会社」という二項対立
という、5種類の、似ているようでいて、中身のかなり異なる、それでいて関連性も否定できない二項対立に整理することによって、よりよい理解ができると思われます。
このように、二項対立している類型を5種類も挙げることができるということは、「『営利事業』の主体」の具体的な現象形態は、その時その時の政治体制、社会体制の中で、さまざまなバリエーションが付加されたり切除されたりしながら、制度化されてきたことの結果であることを意味していることに他なりません。そこで、付加や切除のなされた後の具体的な衣をまとったそれぞれの時代、それぞれの経済圏の「『営利事業』の主体」を目の前にすると、そもそも比較のために抽象化し、類型化するという作業をしようと企てることそれ自体が、果たして可能なことなのかといった疑問も否めないところです。しかし、時系列的観点、論理系列的観点を導入して検討を加えてみた結果、こうした5種類の二項対立を意識することによって、「『営利事業』の主体」は、以下のとおり有意義に整理することでき、そのさまざまな形態の理解を深めることができました。
二項対立する営利事業の主体
「1人の自然人」が、「元手としての財」との間に結ぶ「所有」と呼ばれる関係は、自由で、であるからこそ単純なもので、その「1人の自然人」の意思ですべてのことを決めることができるものです。しかし、「複数の自然人」が、財との間に結ぶ関係は、何の工夫も施さなければ「共有」という関係になるしかなく、全員一致でなければ何もできない状態に陥ってしまいます。何人かが集まって元手を出し合えば、大きな事業が効率的にできるかというと、必ずしもそういうわけではないのです(①の二項対立)。
「グループとしての(複数の)自然人」は、「共有」のアポリアから脱却するために、新たな制度の開発に取り組まなければなりませんでした。それは、例えば「組合(今の日本でいう民法上の組合)」のようなものだったかもしれません。確かに「組合」は、特別な目的の遂行には、適したところもあるものなのでしょうが、普通の事業の主体とするには、使い勝手が悪いものでした。そこに登場したのが「法人」という制度だったわけです(②の二項対立)。
「法人」という概念を抵抗感なしに受け入れられた社会は、「グループとしての(複数の)自然人」から出発して、種々の形態の法人を案出していったわけです。そのなかでも、「『営利事業』の主体」としての法人という観点からすると、その中心にあったのは「会社」という制度でした。一方、「法人」としての「会社」が考案できるようになると、まず、資産を管理することを目的とした「法人」として「持分会社」という制度が形成されました。そして、そこに他人を巻き込んで資金的な関与をさせ、「営利事業」をより大きな規模で営めるようなものにするための道具の組成に関心が移行していき、「株式会社」という制度が案出され、洗練されて今日に至るということのようです。
もっとも、「法人」という概念は、すべての社会に受け入れられたわけではないということにも注意が必要です(中田考 イスラーム法とは何か? 増補新版 183ページ)。「法人」という概念が受け入れられなかった社会では、「会社」に対応する制度(シャリカ)も「グループとしての(複数の)自然人」の集まりとしての「組合」にとどまっていたということです(中田 前掲書200ページ)。当然、論理序列からして、「法人」という概念が受け入れられなかった社会では、「会社」という考え方を受け入れることはできません。そうなると、経済活動にとって、かなり不自由な社会になるような気もします。
「『営利事業』の主体」として「法人」という概念にたどり着くと、そのありようは「持分会社」と「株式会社」に区別されるようになるのですが、「持分会社」とはどんなものだったのか、また、「株式会社」はどのようにして発展し、どんな特色があるものなっていったのかについて、確認しておくことが必要となります。
まず、「持分会社」ですが、少数(または一人)の資産家が、その有する資産(の一部)をひとまとまりのかたまりとし、それに、一個の法人格を与えて、資産をひとまとまりのかたまりとして効率的に管理しようという目的をより一層達成しやすくするために編み出された制度であるということができます。「合名会社」と呼ばれる組織が典型で、「合資会社」がそのバリエーションとされています(現代に近づくと、「持分会社」の中に、有限会社や合同会社と呼ばれる小規模の会社も含められるようになるのですが、原初的形態ではないし、制度趣旨も異なるので、ここでは論じないことにします。)。「持分会社」には、法律が立ち入って保護したり規制したりといった必要がほとんどありませんので、多くの事項を定款自治で決めることができることになっています。もともと自分の資産をその法人に持ち込んだ者(社員)と法人の資産との距離はとても近いものとされています。そうした特質に着目して、戦前の財閥は、「三井合名」、「三菱合資」、「住友合資」、「(合名会社)安田保善社」など、組織の頂点に「持分会社」を利用しました。しかしながら、現在においては、株式会社の規制の自由化の進展で、「株式会社」を巧みに運営(構成)すれば、「持分会社」と同じ機能を持つ組織が作れるようになったので、現在では、「持分会社」は、ほとんど見られなくなりました。
「持分会社」は、「元手としての財」の効率的な管理に着目して組織された会社でしたが、「事業」の効率的な遂行のために会社という組織を利用しようという動きも、勃興してきました(③の二項対立)。
株式会社という制度の生成
「株式会社」についても、とりわけその生成期においては、その制度の組立てや設計には、さまざまな思惑が絡み合っていました。「株式会社」という制度の確立と普及の舞台として、この小論ではイギリスにおける発展に着目してみることにしますが、「株式会社」という制度の確立に費やされた試行錯誤は、大航海時代が始まり、社会が中世から近世に移行を遂げはじめつつあった15世紀のイギリスから、産業革命が始まった19世紀のイギリスまで、400年近くにわたって続きました。それは、とりもなおさず、「株式会社」という組織がいかに複雑な要素からなるものだったのかということを表しています。「株式会社」の確立を理解するためには、こうした複雑な要素を取り出して、その一つ一つが「株式会社」の原型に組み込まれていく様子を見るという視点に立脚することが不可欠です。以下、そうした方法論を意識しながら、創成期のイギリスの「株式会社」という「『営利事業』の主体」の成り立ちの様子を概観していこうと思います(武市春男、「イギリス会社法発展史論」、『城西大学開学十周年記念論文集』所収 1~16ページ)。
王政という権力構造の下で、何らかの事業をやろうと考えた往年の大商人は、イギリス国王から特許(チャーター)を授与されて、一人で国際的な貿易事業を始めました(前もって自分が持っていた「元手としての財」だけで自分だけの「営利事業」を運営したということです)が、やがて、複数の大商人が糾合し、それぞれが持ちよった共同の「元手としての財」によって、共同の計算で「営利事業」を運営する、しばしば「合本会社」(Joint Stock Company)などと呼ばれる組織に発展していきました(「元手としての財」を持ち寄る者の数は増えましたが、全員が「営利事業」の運営にかかわっていました。ここにも、①の二項対立をみることができます)。国王から授与された特許には、多くの特権が含まれていたのですが、そうした特権の中に、「合本会社」への「法人格の付与」という特権があったので、国王から特許を受けた本来の「合本会社」は、「法人格を持った会社(incorporated company)」でした。しかし、国王から特許を受けるには、たくさんの金とコネが必要だったことから、やがて、イギリスでは、17世紀に入ると、国王から特許を受けずに設立された、だから法人格を持つことができないという性質の「合本会社」が現れ、18世紀にかけて、その数が激増しました(ここには、②の二項対立がみられます)。
こうした「合本会社」の中でも「法人格のない会社(unincorporated company)」は、事業を進めていく上で多くのハンディを抱えていましたが、それにもかかわらず、とどまることのない勢いに後押しをされて、会社起業熱は高まる一方になっていきました。加えて、「合本会社」の「元手としての財」も「営利事業」を運営する者たちだけからの取りまとめという枠を超えて、事業運営者ではない、事業運営からすれば外部の人々からの払い込みも歓迎されるようになってきました。会社に外部から「元手としての財」を拠出する者といっても、始めの頃は求められる拠出者の人数も少なく、拠出の単位も大きかったので、拠出者になれたのはごく一部の金持ちに限られていたのですが、拠出の単位は細分化が進み、誰もが払い込むことができるようになり、拠出者の数はどんどん増えていきました。また、拠出者の間で払い込みによって得た権利を売買する取引も頻繁に行われるようになり、拠出者の権利は、株式ととても近いものになっていきました。そうした進化の延長として、株券のようなものも出現しましたし、当初は私的な、後には公的な株式市場のようなものも登場するに至りました(大隅健一郎、『新版株式会社法変遷論』 35~37ページ)。
このようにして過熱していった「合本会社」の起業熱や「合本会社」の株式取引の投機熱は、1720年の南海泡沫事件(The South Sea Bubble)で頂点に達しました(大隅 前掲書 33ページ 注⑼ )。このバブルは、一般のイギリス人の間に生じた過剰投資の熱狂だったわけですが、当時の「会社」のほとんど全てが、「有限責任」という投資者保護の制度を持っておらず、またそういった制度を持つ道もほぼ閉ざされていたことから、この「南海泡沫事件」で、投資者が被った損害は、莫大なもので、大きな社会問題となりました。そこで、「南海泡沫事件」の後、そうした起業や株式売買を弾圧しようとする泡沫法(Bubble Act)という法律が、5年くらいは続きました。しかし、その後,イギリスでは、新たな立法措置によって「会社」という制度をより良いものにしていこうという努力が半世紀近く続きました。そうした法律の制定によって達成しようとされていたのは、特許を受けずに設立された「合本会社」に対する法人格の付与と、「合本会社」を構成する「元手としての財」の拠出者に対する有限責任制度の確立でした。
「合本会社」はごく初期の特権的な国際貿易を目的として組成されたもの以外は、規模の小さなものでした。特定の、具体的な事業の達成のために設立された組織だったので、目的が達成されると清算に入る「当座企業」といわれるものもあったほどだったのです。「株式会社」は、このように、制度が作り上げられたばかりの段階においては、多くは、比較的小規模の、具体的な事業の遂行のために組織された集団でした。とは言うものの、長い道のりではありましたが、ついに「合本会社」の社団性には法人格が付与され、その構成員たる地位を意味する株式は細分化された投資の割合的単位とされ、その保有者としての株主は有限責任によって保護されるという「株式会社」にとってヒスの用件が組み合わされた組織(鈴木竹雄-竹内昭夫著、『会社法〔新版〕』 7~9ページ、20~22ペ~ジ)が確立したのです。これが「初期の株式会社」です。
発展をきわめた組織のとどのつまり
その後、この組織は、産業社会の発展とともに、個々の「会社」としても、そして社会全体としても、規模が大きくなっていくことになりました。「株式会社」は、徐々に巨大化していくとともに、多くの少数株主に支えられなければ成り立たない存在となり、経営者と株主の間の乖離も大きくなっていきました。こうした中で生じた「株式会社」における経営者と大株主と少数株主と債権者との間の利害関係などがリベラルに調整されていった結果、「株式会社」は、バーリー・ミーンズが「支配の進化」と名付けた過程(A.A.バーリ・G.C.ミーンズ著、 森杲訳、『現代株式会社と私有財産』 66ページ以下)を経て、当初の姿とはかなり異なるものに変容していきました。「株式会社」という組織の支配者についても、「株主というより、むしろ経営者なのではないか。」という議論も見られるようになってきたのです。これが「成熟株式会社」です。この「成熟株式会社」は、「初期の株式会社」が時間をかけて獲得した様々な成果をしっかりと受け継ぎながらも、現代化が果たされた結果成立したものだった、ということなのだと思います (④の二項対立)。
もっとも、こうした動きに対しては、反動とでも呼ぶべきものも目に付くようになってきました。「株式会社」にとっての株主との関係性について、「成熟株式会社」のようなあり方に、強い異論が投げかけられるような風潮が巻き起こってきたのです。こうした、新たな「株式会社」に対する見方を推進する原動力となっていたのが、「市場原理主義」あるいは「新資本主義」と呼ばれる現代社会の一部で声高に主張されている動きです。こうした動きを肯定して組み立てられた「株式会社」のことを、私は「成熟株式会社」と区別して、「爛熟株式会社」と呼ぶことにしました(⑤の二項対立)。
この「爛熟株式会社」には見過ごすことのできないいくつかの特徴があります。一つ目は、何のために「株式会社」という組織を経営するのか、という目的から、地道に、具体的な事業を実践していくということの重要性が強調されなくなり、金を儲けることだけが自己目的として強調されるようになったことです。こうした動きの背後にある発想は、フリードマンの、
「フリードマン・ドクトリンー企業の社会的責任は利益を増や すことだ(A Friedman doctrine—The Social Responsibility of Business is to increase its profits.)」(ミルトン・フリードマン 1970年9月13日のニューヨークタイムス紙17ページ掲載 Web上のサイトに転載)
という「教義の託宣」の中に、顕著な形で表現されています。この「ドクトリン」では、企業が何かの事業をする目的は、その事業それ自体を成し遂げることにあるのではなく、その事業を利用して金を儲けることだけにあるのだと断言されているのです。
二番目の特徴は、「株式会社」の支配者は、株主でなければならないという強い信念です。それも、株主全員というのではなく、大株主、あるいは支配株主が「株式会社」の支配者でなければならないというのです。ここで大株主というのは、機関投資家やファンドのことを意味していることには注意してください。創業者が、自ら創業した「株式会社」の大株主あるいは支配株主として君臨しているというのは、むしろ「初期の株式会社」の特質でもあり、「爛熟株式会社」の議論とは、区別した方がよいからです。
こうした風潮の中で、逆に、少数株主の共益権は、同じ「株主」でありながら軽視されることが少なくないという状況が目立つようになってきました。その例のひとつとして、「種類株式」という制度の過度の重視を挙げることができます。「種類株式」という制度は「成熟株式会社」の時代から存在してはいましたが、それほど利用されてはいませんでした。ところが今日、大株主の「株式会社」支配に、よく言えば、多大なフレキシビリティーを与えて、「株主平等原則」を変質させるという、注目すべき事態を実現するための手段として、この「種類株式」という制度が利用されるようになってきたのです。「種類株式」は、公開会社の非公開化(Going Private)の手続きにとってなくてはならないものですし、また、GAFAなどのアメリカの先進的な企業は、この「種類株式」という制度を利用することによって、資本市場でいくら資金調達をしても、中心的メンバーの会社支配が崩されないようにするための仕組みづくりに活用していることが報じられています。
三つ目の特徴は、上場「株式会社」における経営者と大株主の異常な接近です。もともと、上場「株式会社」の資本市場に対する関心は、
資本市場で新株を発行したり、社債を発行したりして資金調達をする場所というところだけにしかありませんでした。しかしながら、このような、旧来の上場「株式会社」、資本市場、株価についての関係性、とりわけ「上場企業の経営者と大株主の新たな関係性」は、「爛熟株式会社」の場合、それまでのものと全く異なるものに変質してしまいました。そうした関係性の変質の趨勢は、時間とともに強くなり、また、そうした趨勢に適合的な制度が創設・洗練されるようになり、また、そうした趨勢を支える経済理論や経営理論も発達してきました。
「上場企業の経営者と大株主の新たな関係性」を支えている制度として、ここでは、3つのものを挙げてみたいと思います。一つは、今盛んに行われている「インべスター・リレーションズ(IR)」です。これは公開会社の経営者による大株主に対する自己PR活動、積極的な働きかけのことです。この働きかけは、経営者が、大株主やその代理人を定期的に特定の場に招聘し、経営者の側から自社の業績を中心とした報告を大株主に説明し、経営者と大株主が、同じ場で情報交換をするという行事のことを言います。二つ目は、証券アナリストという職業の確立です。三つ目に挙げる必要があるのは、比較的新しく作り出された「四半期決算制度」という制度です。
確かに、こうした制度は、情報の「開示」とか、情報の「透明性の強化」とか、情報の「非対称性の解消」とか、現在の社会が最先端の課題として意識している目標に、ぴったり当てはまるもののようにも考えられるのかもしれません。しかし、上場企業の経営者の側が、積極的に、そうした制度を介して、大株主に接近しようとしているという姿勢は、私には、必ずしも、素直に受け止められないところが残ります。というのも、上場企業の経営者に対して生殺与奪の権を有する大株主への経営者の接近は、接近というより、すり寄りという印象がぬぐえないからです。
こうした「爛熟株式会社」を取り囲む制度的枠組みを肯定的に論じる論者は、こうした制度的枠組みの窮極的目的を「企業価値」の極大化と説明します(近藤一仁 「企業価値向上のための経営情報戦略・IRの本質について」 186ページ以下)。こうした、「爛熟株式会社」の経営者の株主とのあるべき関係について、フリードマンは、前掲のものとは微妙に異なるフリードマン・ドクトリンで、
「企業の最大の責任は株主の満足にある(an entity’s greatest responsibirity lies in the satisfaction of the shareholders.)」(CFIというWeb上のサイトからの引用)、
と「教義の託宣」をしています。この「ドクトリン」のメッセージが語るところによれば、「企業価値」の極大化を目指す目的は、株主を満足させることに尽きるようにも見てとれるわけですが、それだけではないようにも思えてきます。というのも、「株主に満足してもらえるように、自らの行動を律する。」という上場企業の経営者の行動指針は、見る角度を変えてみると、大株主に生殺与奪の権を握られているだけに、上場企業の経営者の保身、立場の安全の確保ものためになされているもののようにも思えるからです。こうしてみると、「株式会社の支配者は株主である」という考え方と「上場企業の経営者と大株主の間に新たな関係性を構築しなければならない」という考え方の行き着く果ては、「自己保身に走る経営者と金儲けにまい進する大株主の癒着」しかないようにも思われるのです。
二つの株式会社観
もちろん、今でも、「『株式会社』のあるべき姿は『成熟株式会社』であって、『爛熟株式会社』というあり方は、間違っている。」という人もいます。「二つの『株式会社』観の対立の背景には、『成熟株式会社』を良しとする考え方と『爛熟株式会社』を良しとする考え方の対立があるのではないだろうか。」これが、私の冒頭の問題意識についての、私なりの結論です。私は、「成熟株式会社」派なのですが、今や、二つの「株式会社」観を比べると、遺憾なことではありますが、「爛熟株式会社」の方が優勢のようです。「成熟株式会社」は「爛熟株式会社」にとって代わられようとしている節があるどころか、もう、すでに、「爛熟株式会社」が、世の中を席巻している感があるのです(⑤の二項対立)。
ここまで論を進めてみると、冒頭でご紹介した「株式会社」に対する理解のかなり深刻な混乱のよって来る根拠の一端も明らかにすることができたように思われます。現代社会のトレンドは、どちらかといえばリバタリアンと総称される「市場原理主義」、「新資本主義」と呼ばれる側に移行しているのかもしれません。しかしながら、それは、進歩というような楽観的なものなどと到底言えるものではありません。そこにあるのは、拝金主義、ファンドやアクティビストなどと呼ばれることもある物言う株主、新たに生じつつある社会格差、限度を超えた自己責任の押し付け、と挙げはじめればきりがないほどの問題をその内に含んでいます。生活感覚の問題として、私には、とてもついていけません。
資本主義生誕の地

同じ経済現象を対象とした言葉であるにもかかわらず、「資本主義」という用語の使われ方は、使い手によってかなり異なるという印象があります。どうしてそのように用語法のすれ違いが生じてしまうのかについて、常々考えていることを、まとめてみたいと思います。
私が、用語法のすれ違いの理由として最も注目しているのは、「資本主義」は、どんなところで、発展してきたものなのかについての、事実認識、着眼点の論者による不一致です。議論は、「身近なところの内側から生じた。」と考える議論と、「身近なところの外側で、身近でないところとの接触から生じた。」と考える議論の二つに分かれるように思われるのです。
「身近なところの外側で、身近でないところとの接触から生じた。」と考える議論の方が、多分一般的に受け入れられやすいものだと思いますので、ここでは逆に、まず、「身近なところの内側から生じた。」と考える議論からについて説明させていただきます。この議論には、マックス・ウェーバーなどによって重用された、「封鎖的家族経済」などと訳される「オイコス」の構造を利用するとイメージしやすくなると思いますので、ここでも「オイコス」を説明のキーワードとして、使わしていただきます。
「オイコス」はもともとギリシャ語で、「家」(いえ)のことを意味していました。「家」を「身近なところ」と考えるわけです。ところで、ギリシャでは、「貨幣」(ノミズマ)が発達していたのですが、「貨幣」は、「オイコス」の外側(ギリシャの場合のポリス)における、財の公正で円滑な分配の媒介の手段として、不可欠のものとされていましたが、「オイコス」の内側では使われていませんでした。「オイコス」の内側の場合、財の分配は、家長が判断して決めていましたので、「貨幣」は必要とされていなかったからです。つまり、「身近なところの中から生じた。」と考える議論にとって、「貨幣」の存在は、「資本主義」にとって、絶対的なものとは考えられていないのです。
「オイコス」は、のちに、ギリシャに存在した「家」という具体性を離れて、「自己充足的な経済圏」を意味する経済史学の専門用語として使われるようになりました。この意味では、封建領主の領土も「オイコス」ですし、「国民経済」も「グローバル経済」との対比という文脈の中では「オイコス」ということにいなります。
資本主義のルーツを「オイコス」の内側に求める経済理論の典型は、カール・マルクスの「資本主義論」です。マルクスによれば、資本の原始的蓄積は、「農民層の分解」あるいは「中産的生産者層の両極への自己分解」の中で、つまり、当時、社会の内部で、生産活動を担っていた者たちの中で進んでいきました。古い貨幣経済とそれに支えられた古い商業は、マルクスのような立場をとる論者からは、「資本主義」とは無関係のものとされました。こうした「人類の歴史とともに古い」経済制度には、「前期的資本」とか「遠隔地貿易」といったネガティブなレッテルが、貼られました。
ちなみに、マルクスは、商業を蔑視し、商業資本主義とは未発達な社会に寄生する活動でしかないもので、「久しい以前から、資本主義的生産様式に先行し、そして極めて種々に異なる経済的社会構造において見出される、資本の大洪水(旧約聖書にある「洪水伝説」(創世記 6 洪水)のことを指しています。)以前的諸形態に属する。」 (カール・マルクス 著 向坂逸郎 訳 資本論 第三巻 第二部 747ページ)といったことを繰り返し論じています。こうしたマルクスの発想は、マルクスの「商売人嫌い」、「生産者好き」からきているようです。マルクスは、商業のことを「流通費」として、一種の必要悪として扱っています。この考え方は、決して分かりやすいものではありませんが、マルクスは、商業のことを「この価値を作るのではなくただ価値の形態変化を媒介するだけの労働…。」「この売買担当者…の労働の内容は、…生産の空費に属する。」「いかなる事情のもとでも、このために費やされる時間は、転化された価値には、何物をも付加しない流通費である。」「それは諸価値を、商品形態から貨幣形態に転嫁するに必要な費用である。」と説明しているのです(前掲マルクス 著 資本論 第二巻 149~153ページ)。要するに、マルクスは、価格差を利潤の源泉とすること、それを生業とする商業、とりわけ「オイコス」の外側で行われていた投機的商業に、およそ積極的な価値を認めませんでした。
この論点に関する限り、旧来の「政治的ないし投機的な志向を有する『冒険家』資本主義」を「賤民資本主義」とまで言い切ったマックス・ウェーバーの立場は、マルクスとほとんど同じでした(マックス・ウェーバー著 宗教社会学論集 第1巻 プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 戸田聡 訳234ページ)。アダム・スミス及びスミスに続く古典派の経済学者の場合はどうだったのでしょうか。マルクスは、考え方の本質は同じだったと考えていたようです(カール・マルクス 著 マルクス・エンゲルス全集 第26巻 第1分冊 剰余価値学説史 大内兵衛・細川嘉六 監訳 48ページ以下)。もっとも、こうした、商業を全否定してしまうの経済理論は、19世紀までは通用したものだったのでしょうが、現在の資本主義の分析には、物足りないところもあるような気もします。しかしながら、「資本主義」とは何なのかを理解するために、「資本主義」がどうやって生じたものか、を知るためには、欠かせない議論なのだと思います。
一方、「資本主義」を「身近なところの外側で、身近でないところとの接触から生じた。」と考える議論は、資本主義のルーツを「オイコス」の外側に求める経済理論と整理することができます。その代表格は、マルクスによれば、彼が「重農学派以前」と呼んだ経済学者たちということのようです。マルクスは、彼らについて、「…利潤は、純粋に交換から、商品をその価値よりも高く売ることから説明…」しようとするところに根本的な誤りがあると論じています(マルクス 前掲 剰余価値学説史 8ページ)。また、カール・ポランニーは、資本主義のルーツを「オイコス」の外側に求める経済理論をミハエル・ロストフツェフ(ローマ帝国社会経済史 を主著とするロシア革命直前の世代に属するロシアの学者で、他に 古代における資本主義と国民経済 という著作もあります。)に代表させ、資本主義のルーツを「オイコス」の内側に求めるマックス・ウェーバーと対比することによって紹介しました(K・ポランニー 著 玉野井芳郎・中野正 共訳 人間の経済 Ⅱ 484ページ)。
この、資本主義のルーツを「オイコス」の外側に求める考え方は、そもそも、こうした問題意識を持つことなく、経済を論じる論者にも大きな影響を与えています。おそらく、ミルトン・フリードマンの展開した「マネタリズム」などが、その頂点に立っているのかと思われます。